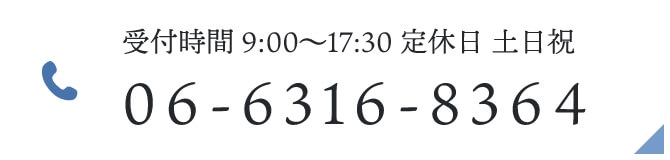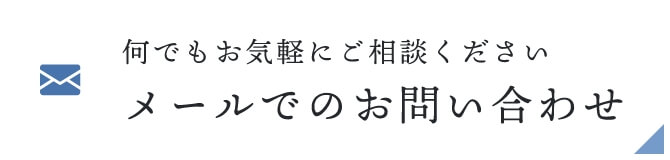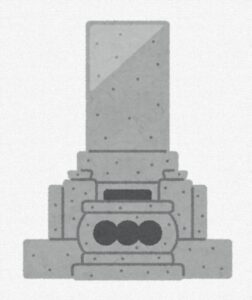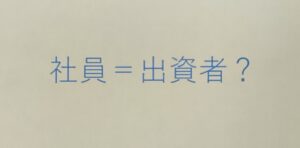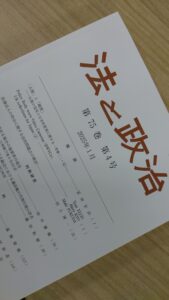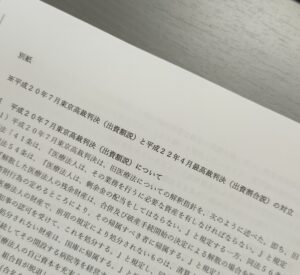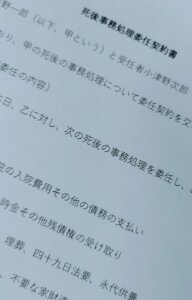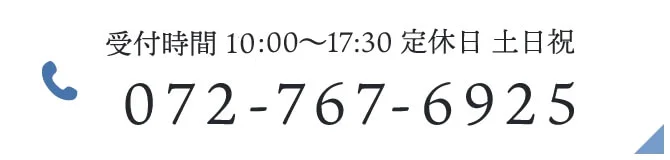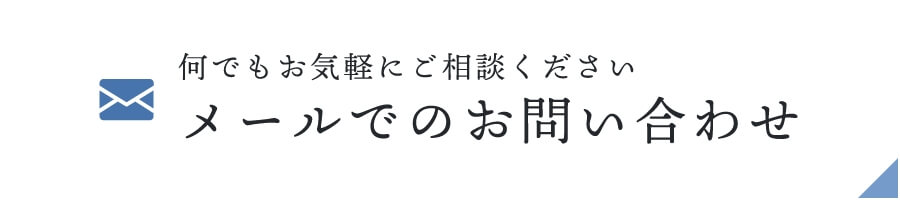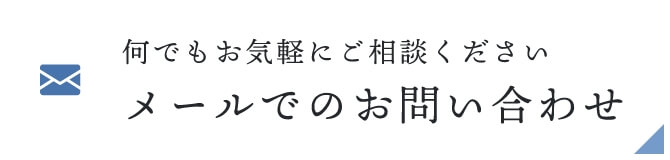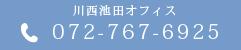遺言能力①基礎知識

DSC_0519
遺言には判断能力=意思能力が必要
例えば、判断能力(法的には「意思能力」乃至は「事理弁識能力」と表現されます。)を欠く常況(7条)にある者が後見開始の審判を受けると、その者は成年被後見人として、その法律行為を取り消すことができます(8条、9条)。
つまり、成年被後見人は、行為無能力者とされ、一人で確定的に有効な法律行為をする能力がありません。ところが、遺言については、この行為能力に関する制限は解除(962条)され、例えば、成年被後見人としては、判断能力を一時回復した時、医師二人以上の立会いの下、それらの医師が判断能力を欠く状態になかった旨を遺言に付記し署名・押印すれば、遺言することができます(973条)。
結局、民法では、判断能力=意思能力があれば遺言能力はあり、遺言はできるとされています。反対に、判断能力=意思能力がなければ、遺言能力はないとされ、遺言が存在したとしても、当該遺言は無効となります。
どのような場合に遺言能力は否定されるのでしょうか。遺言能力の有無は、①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否・内容・程度、②遺言内容それ自体の複雑性、③遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等といった諸事情が考慮され、判断されます。以上の事情について、簡潔に説明したいと思います。
1 遺言時における遺言者の精神上の障害の存否・内容・程度
これらは、精神医学的観点と行動観察観点から、考察されます。
1)精神医学的観点
遺言能力=判断能力に影響を与えるものとして指摘されているものは、認知症、精神分裂病から内臓疾患に至るまで、多岐にわたります。認知症の類型としては、アルツハイマー型、脳血管障害型等があります。その中でも最近争われることの多い「認知症」による遺言能力の有無についての目安として、長谷川式簡易スケール(以下、長谷川式テストといいます。)を重要視する見解があります。
長谷川式テストによれば、
20~30点-異常なし、 16~19点-認知症の疑いあり、 11~15点-中程度の認知症、 5~10点-やや高度の認知症、 0~4点-高度の認知症 とされています。
そして、大まかな目安として、15点以下の場合には遺言能力に疑いが生じ、10点以下の場合には遺言能力がないと指摘するものとなっています(河原崎「認知症の母の公正証書遺言の効力/弁護士の法律相談」参照
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/yuigonotar.html
現実の裁判例における遺言能力の判断は遥かに詳細になされており、単純にこの見解のとおりであるとは言い難い面もありますが、それに沿った裁判例も多く1つの簡易な目安としてはとても役立ちます。
2)行動観察観点
また、上記精神医学的観点を1つの目安としつつ、医療記録、看護記録、介護記録及びそれらを作成した者らの供述等から伺える遺言者の当時の行動等を観察して、遺言能力=判断能力が総合的に判断されることになるでしょう。抽象的にいえば成年被後見人について962条が指摘する「判断能力を一時回復した時」ということになりますが、認知症についていえば、参考となる判例がいくつかあります。この点については、次回のブログ(遺言能力②(認知症と遺言無効に関する裁判例https://kawanishiikeda-law.jp/blog/875)を参照ください。
2 遺言内容それ自体の複雑性
これらは、上記「遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度」とも大きく関連します。判断能力が低くても遺言内容がシンプルであれば遺言能力が肯定される例も多く、またその逆もあります(これを「遺言能力の相対性」といいます。)。参考になる例としては、以下のものを指摘できます。
1)遺言能力を肯定した例
- 「全財産を遺贈する」(大阪高判平成2年6月26日・家月43巻8号40頁)公正証書遺言・精神分裂病のケース
- 「遺言執行者の指定も含めて全部で八か条、相続に関係する者も、妻、子及び孫という近親者だけで、その対象も不動産と預金のみ」(東京高判平成10年8月26日・判タ1002号247頁)公正証書遺言・加齢に伴う生理的な徴候は認められたが、未だ痴呆の領域には至っていないケース
- 「一切の財産をBに遺贈する、Bを遺言執行者とする、葬儀に関する付言事項といった3か条」(京都地判平成13年10月10日)公正証書遺言・認知症のケース-長谷川式テストの結果は4点
2)遺言能力を否定した例
- 「本件遺言の内容がかなり詳細で多岐にわたる(特に、株式についての遺言内容の分配を計算する計算関係は複雑である)」(大地判昭和61年4月24日・判タ645号221頁)公正証書遺言・肝不全症状等による重篤状態のケース
- 「本件遺言が前記のとおり必ずしも単純な内容のものではなかった(但し、判決掲載誌では省略のため詳細不明)」(東地判平成4年6月19日家月45巻4号119頁)公正証書遺言・認知症のケース-遺言書作成当時長谷川式テストもできない状態で判断力等は4、5歳程度と診断
- 「本文14頁、物件目録12頁、図面一枚という大部の公正証書遺言」(東京高判平成12年3月16日判タ1039号214頁)公正証書遺言・認知症のケース-遺言書作成当時の長谷川式テストの結果は4点
3 遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯
この点に関して言えば、遺言を肯首するだけの動機がよく指摘されます。
たとえば、遺言者A(当時96歳)が知人Bに3,800万円余りの預金債権を遺贈する旨の死亡危急時遺言について、東高決平成3年11月20日(家月44巻5号49頁)が、高額の預金債権を「親族ないし同居人を差し置いて、何らの縁戚関係等も存在しないB一人に対してのみ、右のような高額の本件預金債権を遺贈するということは、甚だ不自然というべきであり、右遺贈について、それ相当の原因ないし理由が存在すると認めることは困難である」として、その効力を認めなかった例が参考になります。
また、遺言者C(当時78歳)がその財産をDに包括遺贈する旨の公正証書遺言の効力が争われた事案について、名古屋高判平成5年6月29日(家月46巻11号30頁)は「遺言者はDと、これまでほとんど深い付き合いがなかったので、Cの全財産をDに包括遺贈する動機に乏しい、全財産を遺贈し、Cの姉弟の扶養看護から葬儀まで任せることは重大な行為であるのに、姉にはなんら相談をしていないのみならず、Dから話が出てわずか五日の間に慌しく改印届をしてまで本件遺言書を作成する差し迫った事情は全くなかった」として、Cの遺言能力を否定した例も参考になります。
遺言能力の関連記事はこちら
https://kawanishiikeda-law.jp/blog/877
宝塚市・川西市の相続・遺言相談は村上新村法律事務所・川西池田オフィスまで
https://g.page/murakamishin?gm
大阪市・福知山市の相談は踊る
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/