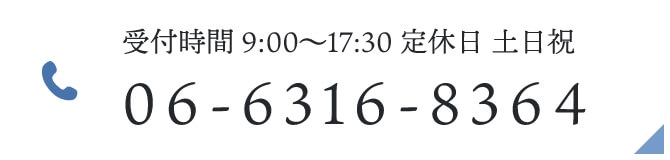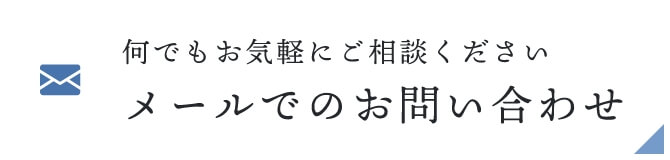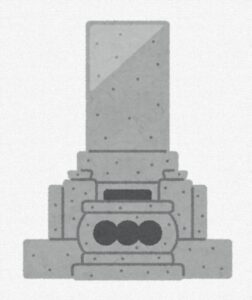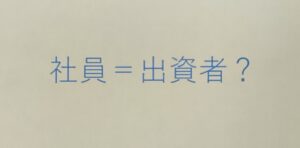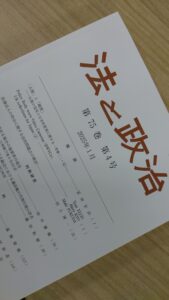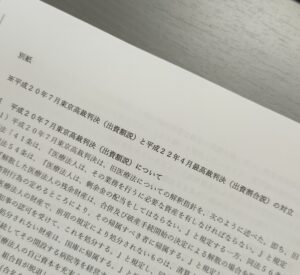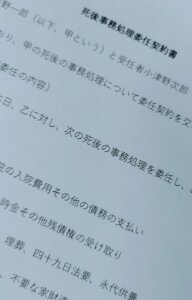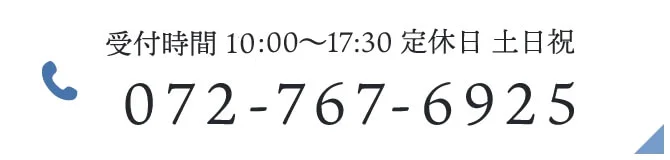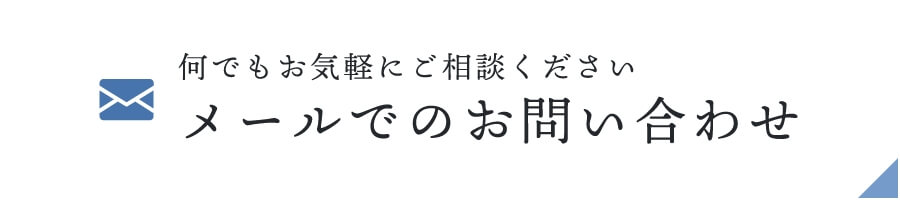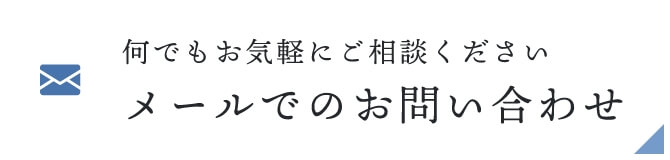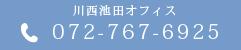遺産分割審判④使途不明金(預貯金の調査・付随問題)

相続の相談を受ける際「被相続人の預貯金が思っていた以上に少ない。」といった話をよく聞きます。これは、使途不明金といわれ、家庭裁判所では「付随問題」とされるものの1つで悩みの種とされています。この点について、簡潔に説明したいと思います。
なお、遺産分割審判に関するその他の投稿はこちら
遺産分割審判①判決との違い・手続 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2608
遺産分割審判②対象になるか否か https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2633
遺産分割審判③預貯金 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2678
1 預貯金の調査・付随問題
(1)預貯金の調査
素人の方が、使途不明金を問題にして遺産分割調停等を起こすとき、裁判所が預貯金を調査してくれるだろうという期待があります。しかし、使途不明金とは、詰まるところ「見当たらないもの」ですが、遺産分割とは、現存する遺産を分割する手続であって「ない」ものは分割できません。裁判所の本音としては「当事者がわからないものは裁判所だってわからない」というところです(片岡外編著「新版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版株式会社58頁)。
【弁護士法23条照会の利用】
そこで、この「見当たらないもの」について、凡その目途は当事者がつけなければなりません。相続人は「被相続人の権利義務を承継」する(896条)ので、その気になれば被相続人の預貯金の内容を確かめることはできますが、この点、弁護士に依頼すれば、弁護士法23条照会というシステムがあり、より簡便に預貯金の内容の照会をしてくれます(預金については、支店の特定まで求められることが多いですが、最近は全店照会に応じてくれる金融機関も増えてきています。)。ただ、金融機関の目途をつける必要があり、また、調査をするためだけの実費(送料込)として、各地域の弁護士会により様々ですが、一件当たり5千円前後かかるので、手当たり次第にという訳にはいきません。
(2)付随問題の説明
このようにして、預貯金の履歴が手に入ります。すると、被相続人の預貯金が、生前多数回または(或いは)多額に引き出されており、また、死亡後に引き出されていることがあります。被相続人である母をA、依頼者を姉B、相手方を弟Cとすると、その引き出しをしたのがCであるとして「使途不明金」の探求を巡り、遺産分割調停が申立てられることになります。
ただ、注意しなければならないのが、遺産分割の審判の対象等になるものについては限界があるということです(詳しくは、https://kawanisiikeda-law.jp/blog/2633/ 参照)。
調停は、当事者が主体となってその決断による合意で紛争処理にあたるものなので、比較的緩やかです。裁判所も、3回ほどは調停に付き合ってくれます(前掲片岡59頁)。しかし、それが審判の対象等にならないものであれば、裁判所としても当事者間に合意が成立しない限り、最終的に紛争を処理できません。だからこそ、そのようなものを「付随問題」といい、ただ「問題」にはなるが「付随」に過ぎないからこそ、その点に関する合意の見込みが薄ければ取下げを勧告されるということです。
それでは、どのようなものが審判の対象等になり、或いは、ならないのでしょうか。引き出しが、死亡前か死亡後かに分けて検討したいと思います。
2 預貯金の死亡前の引き出し
| 被相続人である母Aの預貯金が、Aの生前多数回または(或いは)多額に引き出されていました。依頼者である姉Bは、相手方を弟Cとし、Cが預貯金の引き出しをしたとして「使途不明金」の探求を巡り、遺産分割調停を申し立てました。 |
Bとしては、先ず引き出しはCが勝手にしたものであると主張します。
(1)相手方が勝手に引き出したことを認めた場合
この主張に対し、Cがこれを認めれば、それは生前AがBに対して不当利得乃至は不法行為による金員請求権を有していたことになりますが、これは金銭債権その他可分債権ですので、審判の対象にはなりません。
ですから、相手方Cが任意に支払ってくれる様であれば、その方法について調停で話し合い解決するということになります。しかし、その支払が期待できない様であれば、Bは調停の取下げをして、Cに対する金員請求訴訟(但し、引き出された額のうちBの相続分である1/2についてのみ)を起こすことになります。
ただ、Cが単純にこれを認めるのは稀で、大概は、以下に述べるとおり「特別受益」に関する主張か「被相続人の為に使った」という主張がなされます。
(2)特別受益に関する主張・反論
① Cが「もらった」という主張
このような主張が認められるためには「Aの了解のもとにCが預貯金を引き出したというだけでは主張として十分でなく、それがAの贈与の意思に基づくものであったということまでの主張が必要である」とされています(東京家庭裁判所家事第5部編著「特集遺産分割事件処理の実情と課題」判タ1137号92頁)。
② Bの特別受益であるという反論
そしてCが「もらった」ということを主張するのであれば、それは「贈与」を受けたということになります。更に、それが「生計の資本としての贈与」であれば、「もらった」分が特別受益として具体的相続分を算出する過程で差し引かれる結果、Cの具体的相続分は0円、即ち、何も相続できないということも生じます(903条)。具体的相続分を算出することは審判等で必要なことなので、このような主張であれば、使途不明金の探求は調停・審判でなされます。
しかし、Cに対する超過特別受益があったとしても、Bはその分の返還を求めることはできません(903条2項)。従って、例えば、遺産分割を求める財産が、その使途不明金のみであって、それが「もらった」ものであれば、Cのところに残存していても、Aの遺産としては「ない」のですから、審判しようにも分割すべき遺産がないということなので、結局、審判にはならないということです。
(3)「被相続人の為に引き出した」という主張
一番よくあるのが「被相続人Aの為に引き出した」という主張です。引き出した金銭が、現金として残っていれば審判の対象になりますし、これが後に「A遺産管理人C」名義の口座にあれば、遺産分割審判の対象になります(最2小判平成4年4月10日家月44巻8号16頁、https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2633/ )。
① 引き出した現金等が全てなくなっている場合
問題は、引き出した金銭が全てなくなっている場合です。これが被相続人の「為にした」ものでなければ、勝手にしたということなので、前述したとおり、BはCに不当利得乃至は不法行為による金員支払の訴えを提起することになります。
【現金等を無理に探すよりも発想の転換を】
Cがなくなったといっているだけで、現実には手元に残っているかもしれません。この点、当事者は躍起になって現金等を探そうとします。しかし、無理やり現金等を発見したところで、それは遺産分割審判の対象になりますが、そこで「Cの下にある現金等をBに分割する」という審判をもらったとしても、すんなりCがそれをBに渡すとは考えにくいです。そうなると、結局、BはCに訴訟を提起せざるを得ないので、無理やり探して審判まで持ち込むことは、その分だけ無駄を費やすことになります。その意味で、Cが「なくなった」というのであれば、その主張を呑み込んで早めに、訴訟等に切り替えるという発想の転換が必要な場合もあります。
② 被相続人の「為にした」という主張はどのような場合に認められるのか
この点、Cから支出明細が出てきたとすれば、その主張の真偽はそれなりに判断できます。しかし、それが出てこない場合(特に長期に亘った多額の引き出しの場合は明細が出てきにくいと思われます。)は、Aの生前の生活レベルを認定し、そのような支出がその生活レベルに見合ったものかどうかにより判断されることになります。
その上で、被相続人の「為にした」ものでは「ない」ことがはっきりした場合は、「勝手にした」ことになるので、Cは不当利得乃至は不法行為による支払義務を負担することになります。Cが支払ってくれる等、任意の履行が期待できないなら、Bは調停等を取り下げてCに対する訴訟を起こすことになります。
難しいのは、「為にした」のかどうか、真偽がわからない場合です。
1つ目の考え方は「勝手にした」場合でないと、BのCに対する金員支払請求は認められません。だとすれば、「為にした」かどうかわからない=「勝手にした」かどうかもわからないということで、Bの請求は認められないという考え方です。
もう1つの考え方は、とりあえず、Cが預貯金を引き出したのは事実である。これを正当化できるのは「為にした」場合だけである。なので「為にした」かどうか明らかでないときは、Cは自らの行為を正当化できないので、Bの請求は認められるという考え方もあるかと思います。
3 預貯金の死亡後の引出し
| 被相続人である母Aの預貯金が、Aの死亡後、金融機関がAの死亡を知って支払停止をかける前に引き出されていました。依頼者である姉Bは、相手方を弟Cとし、Cが預貯金の引き出しをしたとして「使途不明金」の探求を巡り、遺産分割調停を申し立てました。 |
金融機関がAの死亡を知って支払停止をかける前にCがこれを引き出すという場合も、割と見かけます。やはり、このようなときでも、先ずBとしては「Cが勝手に」引き出したと主張します。
(1)預貯金を引き出したCの主張
これに対して、Cの「もらった」という主張は、遺言等でもない限り、認められないと思います。ですから考えられるのは「為にした」という主張ですが、Aは既に死亡しているので、その対象はAではありえません。B、Cという相続人全員の「為にした」という主張がなされます。例えば、葬儀費用、固定資産税の支払の為にしたという主張です。
【引き出した現金は審判の対象となるか】
ただ、このような主張が仮に認められ、Cの下に引き出した現金等が残存していたとしても、預貯金から現金へとその性質が変更されていることから、原則として、遺産分割の対象とすることは出来ないという見解が多いと思われます。
(2)預貯金を引き出したCになし得る請求
このように、被相続人の死亡後に預貯金が引き出されているような場合において、引き出した後の現金を費消してしまった時は当然(また現金として残存していた時でも原則として)これらは遺産分割の対象とはなりません。その結果、他の相続人は不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができます。
この場合、使途不明金とその他の案件を併せた調停による解決が考えられますが、話し合いがまとまらない場合、このような使途不明金については、別途一般の調停や民事訴訟を行う必要があります。
| 最3小判平成16年4月20日(家月56巻10号48頁以下、判タ1151号294頁以下) |
| 共同相続人の1人が、相続財産中の可分債権につき、法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には、当該権利行使は、当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから、その侵害を受けた共同相続人は、その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる |
(3)改正相続法
ただ、このような場合に互いに親族として認識のある相続人間では訴訟まで望まないという声も多いことから、令和元年7月施行の改正相続法906条の2で、不法行為に基づく損害賠償請求乃至は不当利得返還請求の「相手方以外の全相続人の同意」があれば、その相手方に対する請求権を含めた遺産分割審判をすることが可能になりました。
民法906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
例えば、Aの死亡後500万円をⅭが引き出した結果、Aの遺産が預金1500万円となった場合において、相続法改正前であれば、先ず1500万円をBC間で遺産分割審判等をし(ABそれぞれ750万円ずつ)、それとは別にBはⅭに対し引き出した500万円の1/2の250万円を請求することになるのでしょう。ところが、相続法改正後は、Ⅽが引き出した500万円を「遺産として存続するものとみなし」た結果(みなし遺産を含め合計2000万円)、その遺産をBⅭ間で分割し、Bが現実に存在する預貯金1000万円を取得し、残金500万円をⅭが取得するという遺産分割審判を、Ⅽの「同意」なく(Bの同意のみで)、することが可能なりました。
4 最後に
このように考えると、使途不明金について、最終的に審判で解決される場合はあまり多くはありませんが、調停の中で相手方に対する情報を仕入れることも可能です。その結果、仮に、それが審判の対象にはならないものであっても、話し合いに従って調停合意による紛争処理がなされる場合も少なくないので、調停の申立自体にも、それなりの意味はあるのかもしれません。
相続の相談は、弁護士法人村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm