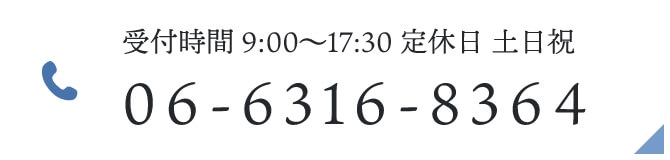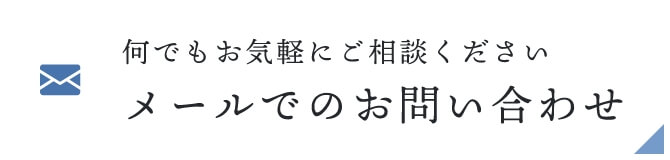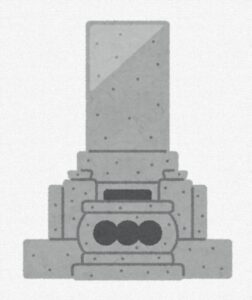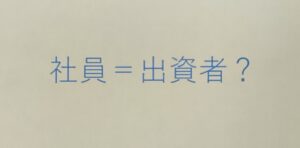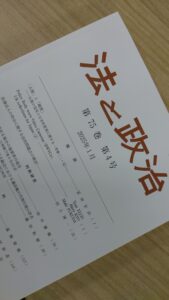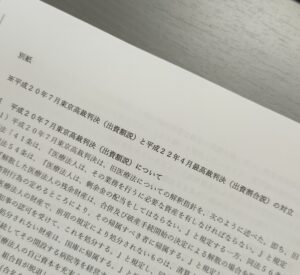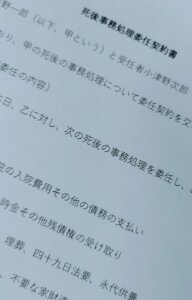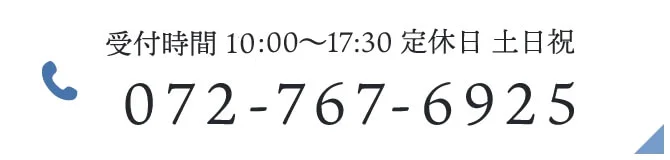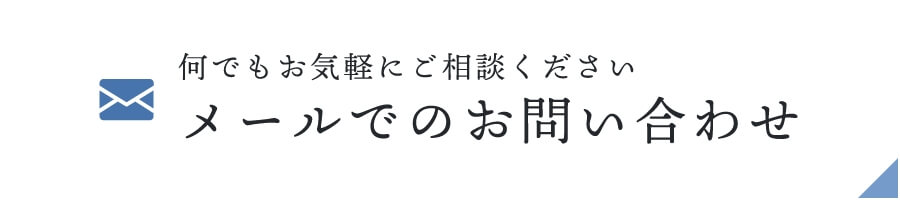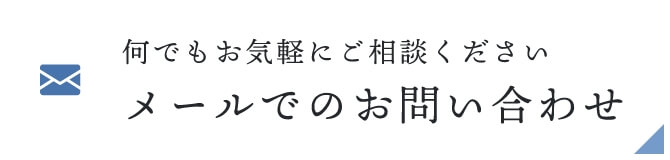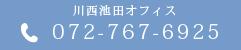任意後見・法定後見
 1 意思能力・判断能力の低下→喪失
1 意思能力・判断能力の低下→喪失
前回のブログでは、身寄りのない方が亡くなった場合について「相続人不存在」という視点から、情報提供してみました(https://kawanishiikeda-law.jp/blog/3097)。今回は、身寄りのない方の生前に役立つ制度として「任意後見・法定後見」の解説をしてみます。
身寄りのない人(身寄りはあるものの、全てが縁遠い人である場合も同じです。)にしてみれば、生前の関心事として、自らの意思能力・判断能力(民法7条では「事理弁識能力」という表現がされています。)が低下・喪失し、独力で生活できない場合にどうすればいいのかということが、大きいと思います。
人の意思能力・判断能力は、低下→喪失という過程を経て死亡に至ることが多いことから、その流れに即して、身寄りのない人をAと便宜上称した上で、任意後見・法定後見の各制度の説明をしたいと思います。
2 見守り契約+任意後見制度
(1)Aの意思能力が正常な段階では、後述する法定後見制度の利用はできませんが、任意後見制度の利用が考えられます。それは、例えば、Aが将来に備えて、信頼できる人(便宜上、Bと称します。)に、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」な状況になったときの代理権を与えます(この代理権を与える契約を任意後見契約といいます。)。そして、現実にAの事理弁識能力が不十分な状態になったときには、Bを裁判所と任意後見監督人とで監視することで、Aの生活をサポートしようとするものです。
任意後見契約に関する法律(以下、単に任意後見法といいます。)2条、4条、7条等では、任意「後見」という言葉が使われていますが、この場合に求められる本人の判断能力の程度が、後述の法定後見制度における「法定後見」程度にまで至る必要がなく「補助」程度のもので足りるとされているのが、1つのポイントです。
このとおり、任意後見制度を利用すれば、将来Aの判断能力が低下→喪失しても、Bが代理するという形で、Aは社会生活を営むことができます。
(2)ただ、任意後見の代理権が発生する程度にまでAの判断能力が低下するのは何時なのか、これは定かではありません。そこで、任意後見契約を交わす際、見守り契約といって、Aの状況をBが普段から電話、面談等により把握し、任意後見制度等の利用に備える契約が広まっています(日本財産管理協会「Q&A成年被後見人死亡後の実務と書式」新日本法規65頁以下)。
最近、警備会社・郵便局等が「みまもり(見守り)サービス(サポート)」を提供しています。主な対象は、遠隔地にいる高齢の両親の生活を見守って貰おうというお子さん方達ですが、これも上記のような見守り契約の一種といえるでしょう。
3 見守り契約+法定後見制度
(1)法定後見制度の中には、補助(判断能力が不十分な場合、民法15条)、保佐(判断能力が著しく不十分である場合、民法11条)及び後見(判断能力を欠く常況にある場合、民法7条、以下、これを、法定後見といいます。)の3つがあります。
Aの判断能力が、補助、保佐程度であれば、未だ自ら判断能力を有している訳ですので、この時点であれば、Aが将来に備えて、信頼できる人(便宜上Bと称します。)に補助人、保佐人になって欲しいと依頼できます。Bが、それを了解し、裁判所から、補助人、保佐人に選任されると、例えば、借金や重要な財産の売買といった一定の行為について、Bの同意が必要となり、これがなければAの行為を取り消すことができます(17条、13条)。また、Bに代理権が与えられる場合もあります(876条の9、4)。
(2)このとおり、例えば、補助、保佐といった制度を利用すれば、Bに同意権や取消権も存在することから、Aに不利な行為は取り消せるので、Aの財産保護が徹底されることになります。
前述したとおり、任意後見制度は、Aの判断能力が正常な段階でも交わせる制度ですが、このような同意権、取消権が認められないという意味で、Bの権限が若干弱いといえます。とはいえ任意後見制度の大きなメリットの1つとして、本人の意向に沿った後見人が選任されるという点があります(法定後見制度における、補助人、保佐人、法定後見人の選任は、裁判所の裁量によるので、この点の保障がありません。)。
しかし、Aには身寄りがないので、誰を補助人、保佐人にするかをめぐる推定相続人等による利害対立も生じないでしょう。このような場合、裁量があるとはいえ裁判所は、補助、保佐の申立の際になされる「Bを補助人、保佐人にして欲しい」というAの希望を受け入れることが多いですから、いっそ判断能力の低下が生じた時点で、補助、保佐の申立をするというのも1つの手です。
(3)ただ、何時、Aの判断能力が補助、保佐程度に至るかは不明なので、これを利用する場合でも任意後見制度の場合と同様に、Bと見守り契約を交わしておいた方がいいでしょう。
Aの判断能力が、法定後見の対象となる「事理弁識能力を欠く常況」に陥ってしまった段階では、Bに後見人になって欲しいという契約を交わすことができないので注意が必要です。ただ、Bが補助人、保佐人になった後に、Aの判断応力が「事理弁識能力を欠く常況」に陥ったとしても、Bは補助人、保佐人として、自ら法定後見の申立ができるので、問題は生じません(民法7条)。
相続・後見の相談は、弁護士法人村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm