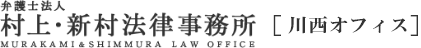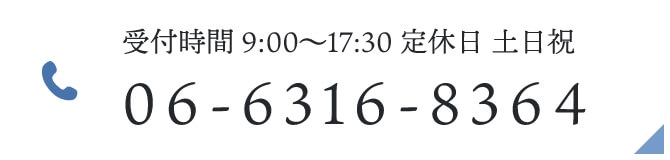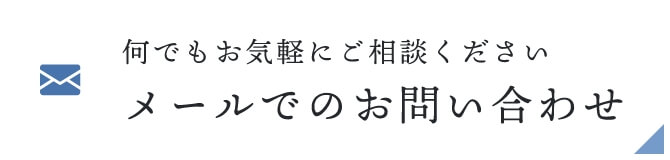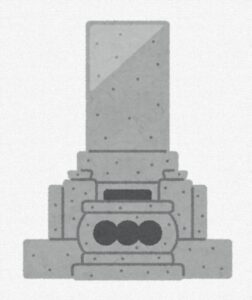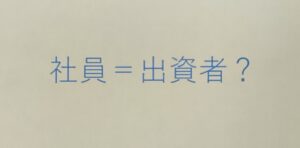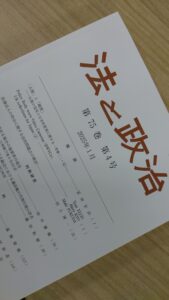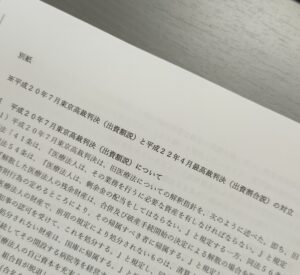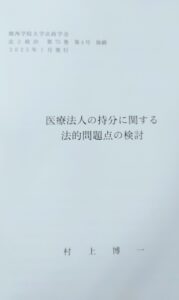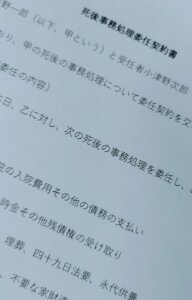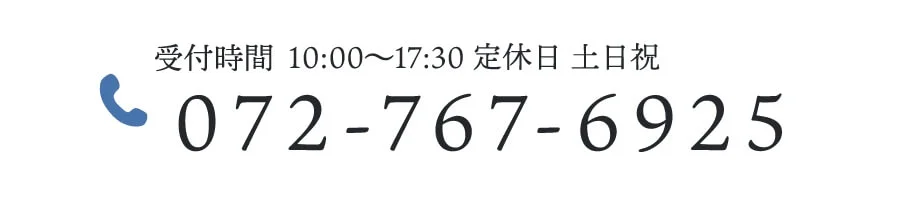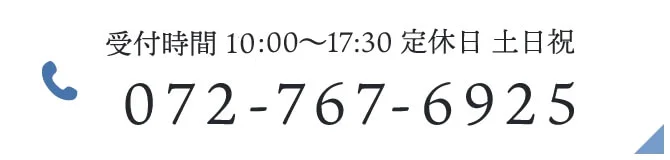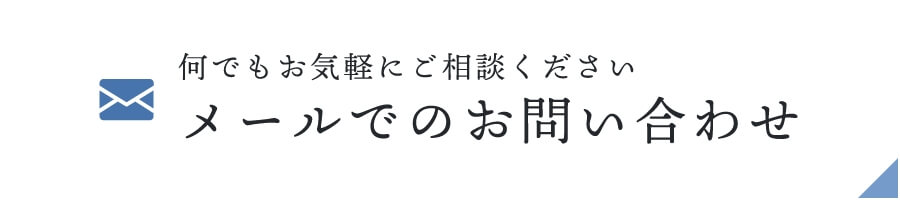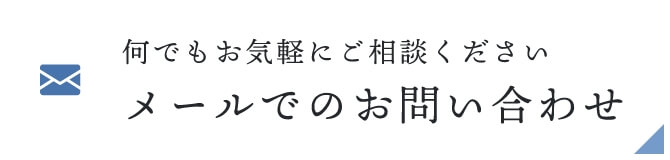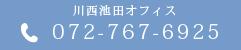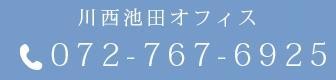推定されない嫡出子と出来婚

1 民法772条2項後段は「婚姻の成立の日から2百日を経過した後又は婚姻の解消…の日から3百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」としています。妊娠期間は十月十日といわれますが、このような経験則をもとにした推定です。そして、同条1項前段は「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。」としています。
では、婚姻後2百日以内に生まれた子はどうなるかといえば、かつては民法772条2項で推定されないものの、戸籍実務上は嫡出子(夫の子)としての届出を受理していました(推定されない嫡出子、最高裁の前身である大審院が、内縁関係の先行していた事案について、懐妊後・婚姻・出生した子を嫡出子としたのを戸籍実務が受け入れ、更にその手続の形式性から内縁関係の有無につき審査をしなくなったものです。)。いわゆる「出来婚」による子への対応でした。
2 ところが、772条2項の嫡出推定が及ぶ子の場合、親子関係の否定は、原告適格(訴え提起等のできる資格)や期間等の制限のある嫡出否認の訴えでしかなしえません(民法774条、777条)。その意味で子の地位は比較的安定しています(結果として、血縁関係のない場合でも、法的には嫡出子と扱われる場合があることになりますが、最高裁は、このような事態を容認しました。その補足意見は「これまで自覚と責任感に基づいて子を育ててきた父の意思を無視して、DNA検査の結果に基づき、子の将来を決めてしまうことには躊躇を覚える」としています、https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1563)。
しかし、推定されない嫡出子の場合は、推定がされない故、親子関係の否定は、誰でも何時でも提起できる親子関係不存在確認の訴えによることになります。ただ、婚姻後2百日以内に生まれた子の99.5%は推定されない嫡出子として婚姻後の夫の子として届出されているという調査結果があり、このような事実からすれば、その子が夫の子である蓋然性が高い(夫婦間での認識が高い)と思われることから、別段嫡出推定の及ぶ子と異なる取り扱いをすることは、不公平ではないかという意見がありました。
3 そこで、令和4年改正により、民法772条2項前段が追加され「婚姻の成立の日から2百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定」した上で、同条1項後段も追加され「女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様(当該婚姻における夫の子と推定)とする。」とされました。従って、婚姻後2百日以内に生まれた子については、従来「推定されない嫡出子」とされていたものが「嫡出推定の及ぶ子」と扱われるようになったといえます。
ただ、婚姻解消等の後、3百日を経過した後に生まれた子の取り扱いはどうなるのか、特に夫の死亡という突然の事情により、やむなく婚姻関係が終了したものの、死亡以前に懐胎していた子の出産が遅れたような場合、それも推定されない嫡出子の範疇として、夫の嫡出子たる身分を取得し得ないかといった点(別段、認知に手続を経る必要がないという実益がある。)については、結論として肯定することは難しいのかもしれませんが、議論の余地が残っているのかもしれません。
なお、親子関係についての投稿はこちら
遺産分割協議・審判の相手方 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1649
藁の上の養子 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1448
人工授精・体外受精等 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1508
男性死亡後の保存精子による受精 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1526
非嫡出子相続差別違憲判決 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1539
嫡出推定とDNA鑑定 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1563
相続の相談は、弁護士法人村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm