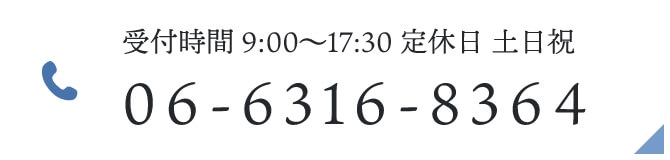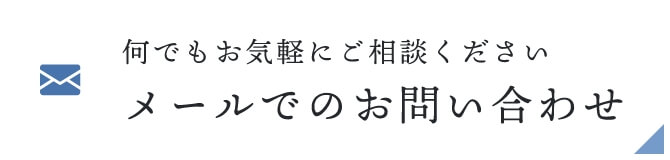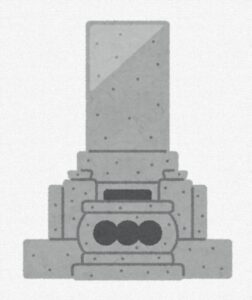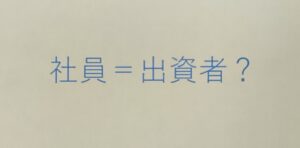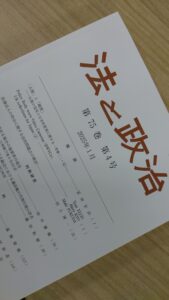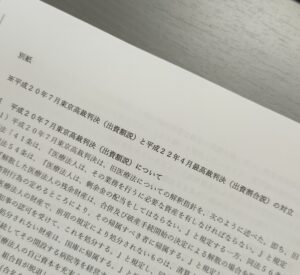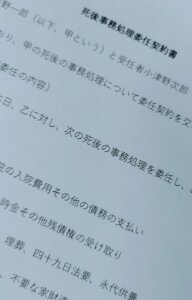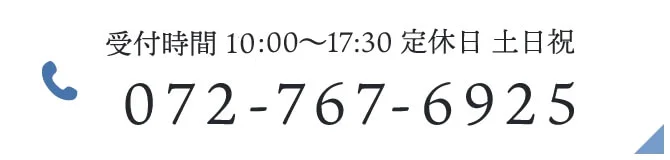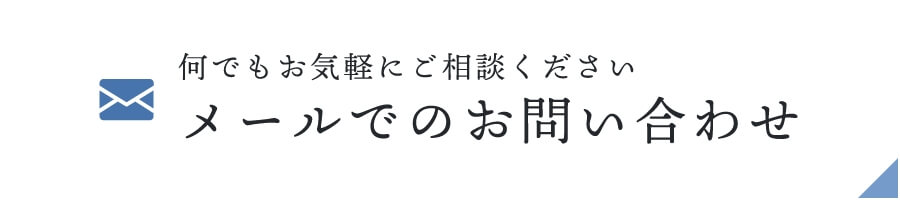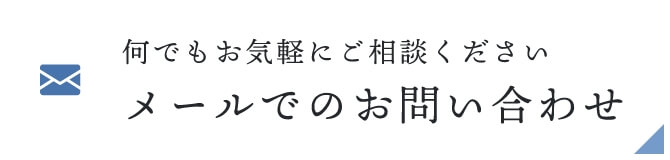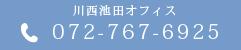嫡出推定とDNA鑑定

DSC_2084
1 はじめに
(1)民法772条1項は「婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」としていて、これを嫡出推定といいます。この推定が及ぶ場合に父子関係を否定するには「夫だけ」が提起できる嫡出否認の訴えによる外なく(774条)、しかもその訴えは子の「出生を知った時から一年以内」に提起しなければなりません(777条)
※ 後日注釈・令和4年民法改正により、原告適格が夫以外の子、母等にも拡大され、期間制限も3年を基準に広げられました(774条、777条)
この嫡出否認の訴えの中で、DNAの結果(夫と子の間に血縁関係なし)を持ち出し、親子関係を否定することは可能ですが、妻や子から、そのようなことをすることはできません。
(2)ただ、嫡出推定には「推定さない嫡出子」という例外が認められていて、例えば「夫の長期不在等妻が夫によって懐妊することが不可能な事実が明らかなとき」は、この推定は及びません(最1小判昭和44年5月29日)。その結果、嫡出否認の訴えの制限は働かず、誰でも何時でも提起できる親子関係存否確認の訴えにより、親子関係の有無を決定できることになります。
そこで、父子間の血縁関係を否定するDNA鑑定が存在する場合に「推定されない嫡出子」として民法772条の適用を否定し、何年か経った後でも、母や子が、親子関係不存在確認の訴えにより、父子関係を否定できるか問題になります。
2 平成26年最高裁判決
(1)この点、最1小判平成26年7月17日(民集68巻6号547号、以下、平成26年最高裁判決といいます。)は「夫と民法722条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚していて別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。」としました。
(2)平成26年最高裁判決が、理由とするのは次の点です。即ち「民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる…夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない…このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから,同法774条以下の規定にかかわらず,親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である…しかしながら,本件においては,甲が被上告人を懐胎した時期に上記のような事情があったとは認められず,他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。」というものです。
3 平成26年最高裁判決のポイント
(1)最高裁は「推定されない嫡出子」について、外観説により判断しているとされています。外観説とは、夫による懐胎が不可能であることが外観上明白な場合かどうか判断する見解で、平成26年最高裁判決でいえば「妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」に限って、民法722条の推定を及ぼさないという見解です。
この見解は、家庭の平和を考慮する見解といえます。
ただ、家庭の平和ということであれば、既に守るべき家庭が存在しない場合は民法722条の推定を及ぼさなくても構わないとも解されます(家庭破綻説)が、平成26年最高裁判決は「夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない」として、このような見解も否定しました。
(2)では、そこまで考慮しなければならない「家庭の平和」はどのようなものなのかということが問題になりますが、この点に関する平成26年最高裁判決の山浦補足意見は、示唆的であり、抜粋すると以下のとおりとなります。
即ち「外観上の事情がなくても,DNA検査等の結果生物学上の父子関係の不存在が明らかである場合には,親子関係不存在確認訴訟の提起を認めるという考え方があるが,これに賛成することはできない。この考え方は,有り体にいえば…外観上夫婦がそろったごく一般的な家庭に生まれた子であっても,たまたま何かの機会にDNA検査をしたところ生物学上の父子関係がないことが判明した場合は,いつでも,利害関係がありさえすれば誰でも,親子関係不存在確認の訴えを提起して,その不存在を確認する判決を受けることができるというものである。この立場は,法律上の親子は生物学上の血縁だけで結ばれているというに等しいものであり,民法772条の文理やこれまでの累次の当審判例に整合しないものである…特に本件のように,年齢的にみて子の意思を確認することができない段階(村上注釈-平成26年最高裁判決等時5、6歳)で,これまで父としての自覚と責任感に基づいて子を育ててきた上告人の意思を無視して,DNA検査の結果に基づき,子の将来を決めてしまうことには躊躇を覚える。とりわけ,法律上の父と母との間においてまだ離婚ないしは婚姻破綻の経緯にまつわる感情的な対立が続いている状態で,子の意思を確認することもなく,その父子関係を決めるのは適切ではないと思う。このような観点からすると,子が,充分に成長して適切な判断力を備えて自己決定権を行使できるようになった後に,自ら父子関係を訴訟において争う機会を設けるということも考えられるが,これは解釈の枠を超えた立法論というべきであろう。科学技術の進歩に応じ,その効果的な利用が必要であることはいうまでもないが,DNAは人間の尊厳に係る重要な情報であるから決して濫用してはならない。たまたまDNA検査をしてみた結果,ある日突然,それまで存在するものと信頼してきた法律上の父子関係が存在しないことにつながる法解釈を示すことは,夫婦・親子関係の安定を破壊するものとなり,子が生まれたら直ちにDNA検査をしないと生涯にわたって不安定な状態は解消できないことにもなりかねない。このような重要な事項について法解釈で対応できないような新たな規範を作るのであれば,国民の中で十分議論をした上で立法をするほかはない。」というものです。
なお、親子関係についての原稿はこちら
遺産分割協議・審判の相手方 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1649
藁の上の養子 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1448
人工授精・体外受精等 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1508
男性死亡後の保存精子による受精 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1526
非嫡出子相続差別違憲判決 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1539
推定されない嫡出子と出来婚 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/3695
親子関係・相続の法律相談は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/
事業再生・債務整理サイト