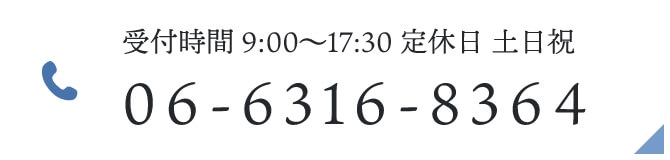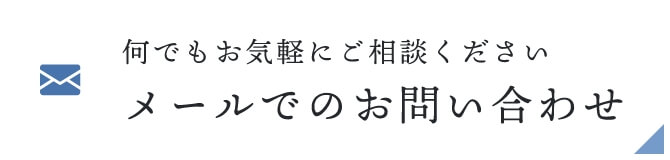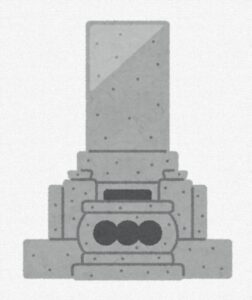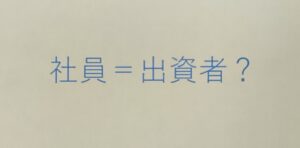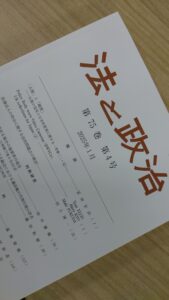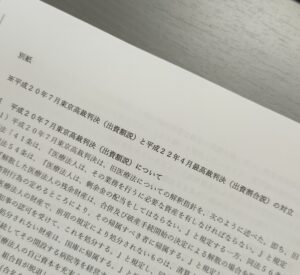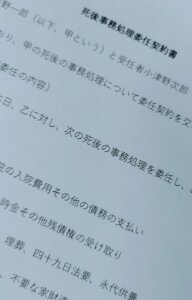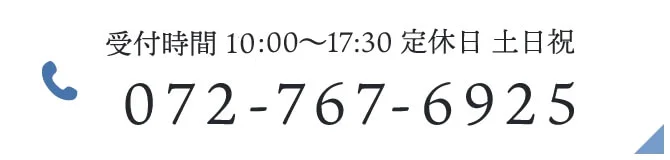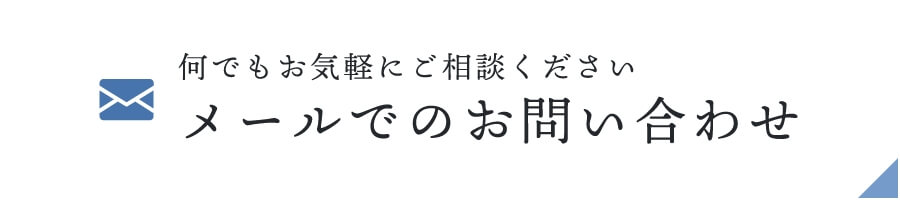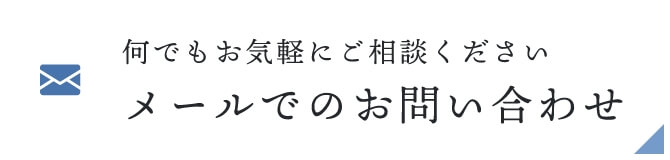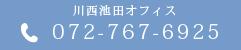遺言執行⑥相続財産の占有・管理

| 設問 |
| 被相続人が不動産を有しており、その子として甲、乙がいました。 被相続人は、甲に不動産を遺贈乃至は特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)を残していたにもかかわらず、被相続人死亡後乙が不動産を単独で占有し事実上管理をしていたとします。 当該遺言には遺言執行者が存在した場合、甲、乙、遺言執行者の関係はどうなるのでしょうか。 |
遺贈乃至は特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)がなされた場合、被相続人が死亡した時点で不動産の権利は甲に帰属します。従って、不動産の実体法上の権利関係についていえば、権利者は甲であり、占有の返還を求める権利があり、乙は無権利者として、占有を返還する義務を負います。
ところが、ここに遺言執行者が入ってくることから、それぞれの権利義務が何らかの影響を受けるのではないかが問題になります。
例えば、当該不動産が収益物件であった場合、賃料の管理をしたり、乙に占有の明け渡しを求めるのは、甲、遺言執行者何れがすべきことでしょうか。
遺言執行者に対する期待と現実
相続の処理をする際には、遺産の調査、相続人・受遺者との連絡という事実行為、電気・ガス・水道等の新使用者への名義変更、準確定申告・相続税の申告、納税等の代行という事務といった広範、かつ、煩雑な事務が存在します。
そして、遺言者のみならず、その家族やその他相続債権者・債務者などの関係者からしても、こうした煩雑な事務を円滑に処理することが遺言執行者には期待されているのではないかと思われます(竹下『「相続させる」旨の遺言の最高裁判決は遺言執行者の関与を排除したものか』判タ823号28頁参照)。
そのような視点からすれば、応急的な処置として、とりあえず、賃料の管理をしたり、乙に占有の明け渡しを求めてみるといったことも、遺言執行者に期待されているといえるでしょう。
しかし、乙との間で紛争が生じた場合はどうでしょうか。この場合、訴訟等をした上で、乙から不動産の管理を取り戻さなければ、遺言執行は終了しないと解すると、その任務は想像以上に重くなります。遺言執行者に就任承諾する者が減ることも予測され、遺言執行制度の運用に困難をきたすことも考えられます。
そこで、相続財産の占有・管理について、最終的な義務を負う者は遺言執行者なのか、それとも受遺者乃至は受益相続人が対応すれば足りるのか、を検討しなければならないことになります。
最2小判平成10年2月27日
この点、参考になるのが、最2小判平成10年2月27日(民集52巻1号299頁)です(以下、平成10年判決)。平成10年判決は、特定財産承継遺言に関するものですが、その射程は遺贈の場合にも及ぶとされています(平成10年判決判例解説233頁)。
| 事案の概要 |
| 被相続人は不動産を有していて、相続人として甲、乙2人の子がいました。 当該不動産について「甲に相続させる」旨の遺言がなされたのですが、乙はその不動産について被相続人から賃借権の設定を受けていたと主張しました。当該遺言には、遺言執行者がいたので乙は遺言執行者を相手として賃借権確認請求訴訟を起こしました。 この場合において、そのような訴訟をする相手方として遺言執行者がふさわしいのか(これを被告適格といいます。)が争われました。 |
そして、平成10年判決は、以下のとおり述べ、賃借権確認請求訴訟をする相手方としては遺言執行者ではなく、受益相続人であると判断しました。
| 平成10年判決 |
| 特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言をした遺言者の意思は、右の相続人に相続開始と同時に遺産分割手続を経ることなく当該不動産の所有権を取得させることにあるから…その占有、管理についても、右の相続人が相続開始時から所有権に基づき自らこれを行うことを期待しているのが通常であると考えられ、右の趣旨の遺言がされた場合においては、遺言執行者があるときでも遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は、当該不動産を管理する義務や、これを相続人に引き渡す義務を負わないと解される。そうすると、遺言執行者があるときであっても、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、右特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人であるというべきである。 |
つまり、遺言執行者には、特段の事情のない限り、相続させる旨の遺言がその目的としていた当該不動産を管理する義務はなく、また、これを相続人に引き渡す義務を負わないとしました。従って、それをすべきは受益相続人だということです。
ですから、平成10年判決を前提とすれば、次のような行為をするのも、遺言執行者ではなく受益相続人ということになります(平成10年判決判例解説230頁以下)。
- 相続人に対抗できる賃借人が目的不動産を占有している場合において、賃料の受領や賃料増額請求等
- 目的不動産の不法占拠者に対する明渡請求訴訟の提起
- 被相続人が生前に提起した賃貸借契約解除を請求原因とする明渡訴訟の承継