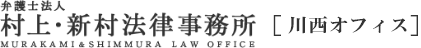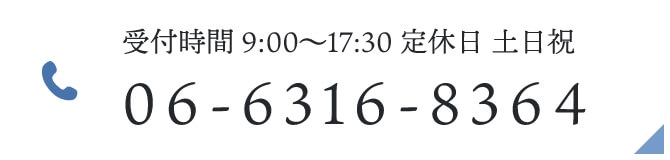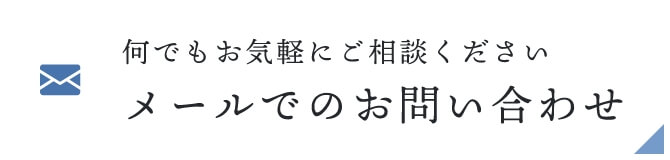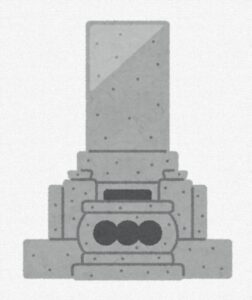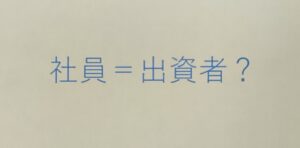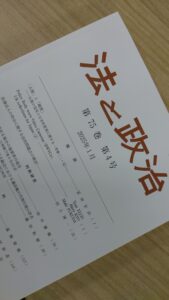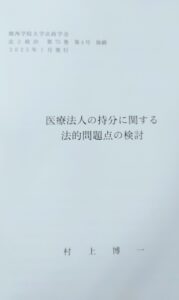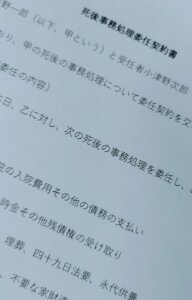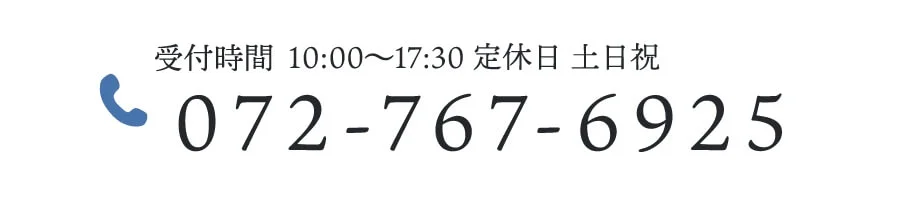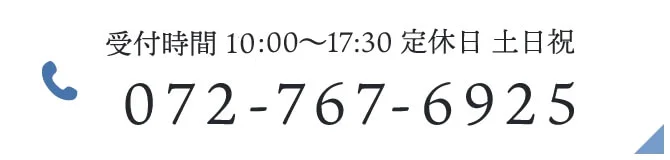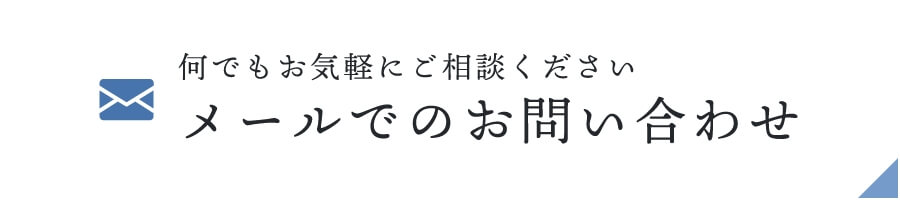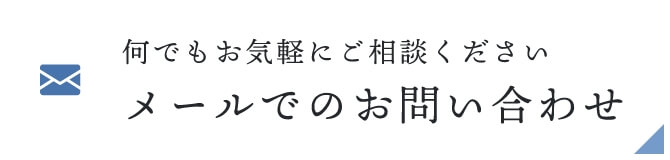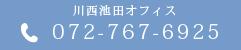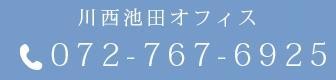医療法人の持分②平成22年4月最高裁判決の概要
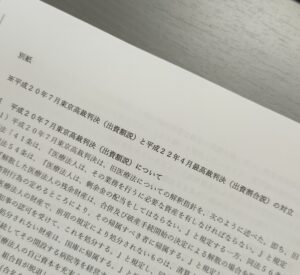
DSC_9513
1 はじめに
前回のブログ(https://kawanishiikeda-law.jp/blog/3723)では、医療法人の持分とは「定款の定めにより、出資額に応じて払戻し・残余財産分配を受ける権利」であると説明しましたが、その権利の内容は「定款の定め」によるところ、平成22年4月最高裁判決の事案の定款では「退社した社員はその出資額に応じて返還を請求できる」とされていたことから、平成22年4月最高裁判決では、この「返還請求権」の「出資額に応じて」という文言の解釈が問題になりました。
2 平成22年4月8日最高裁判決(民集64巻3号609頁)
この点、平成22年4月最高裁判決は「出資額に応じて」という文言を「出資額が占める割合を乗じて算定される額」であると判断しました(第1審判決も同様)。例えば、医療法人Aの持分権者としてB(80%)、C(20%)がいた場合において、総出資額が100万円・純資産額が10億円であったとき、退社時にCが返還請求できるのは、20万円ではなく2億円だということになります。
高裁判決は「出資額に応じて」という文言は「出資額」を意味しており「応じて」という文言は(例えば、B、C)それぞれの出資額が異なることを想定したものであると説明しました。その理屈は、医療法人が、存続する場合(返還請求権)は、解散する場合(残余財産分配請求権)と峻別すべきである(存続中は剰余金の利益処分は禁止されているから)というものでした。背景としては、例えば、上記事例においていきなり2億円の請求が許されるとなると医療法人Aの存続が危うくなることがあるという価値判断があるからと思われました。
ただ、当該文言の解釈としては「出資割合に応じて」と解釈するのが自然であり、それはこれまでの「行政解釈・税務解釈」であって、高裁のような解釈をすることは「昭和25年以来の医療法人制度の法的安定性を動揺させる」ことから、平成22年4月最高裁判決は、高裁判決を破棄したものと思われます(宮川補足意見参照)。
3 平成22年4月最高裁判決の特徴
なお、平成22年4月判決には、少し変わったところがあります。この事案を上記事例になぞらえ簡単に説明すると、Bの持分権が、Cが返還請求権を行使する前に返還請求権になっていたとう事情が存在していました(ただ、Cの返還請求権行使後に時効消滅)。従って、医療法人Aには別途8億円の負債(返還債務)が存在すると考えるべきだとして、Cの返還請求権を2億円の範囲にとどめました。この点、第1審判決は、Bの返還請求権が時効消滅したのであるから、Cの返還請求権の割合は20%➡100%になる(医療法人AはCに10億円を返還しなければならない)としていた点を改めたともいえます。その意味で実質的には、平成22年4月最高裁判決は、第1審判決と高裁判決との中間的なところに着地したともいえます。
なお、医療法人の持分に関する法解釈的提言については、弊所代表社員弁護士村上博一の論考・法と政治75巻4号「医療法人の持分に関する法的問題点の検討」をご覧ください(https://kwansei.repo.nii.ac.jp/record/2001123/files/3.0%20%E6%9D%91%E4%B8%8A.pdf)
医療法人の持分①相続に関連する問題の所在( https://kawanishiikeda-law.jp/blog/3723 )
医療法人の持分③平成22年7月最高裁判決の概要( http://kawanishiikeda-law.jp/blog/3749 )
医療法人の持分④社員と出資の関係(https://kawanishiikeda-law.jp/blog/3801 )
医療法人の相続・事業承継の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm