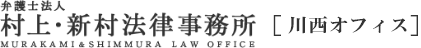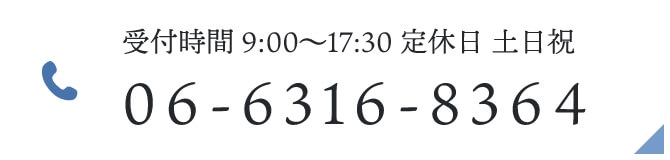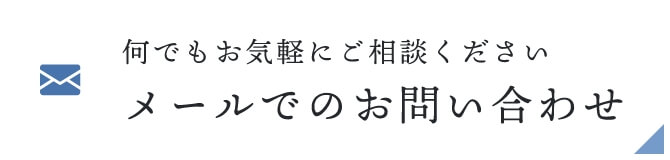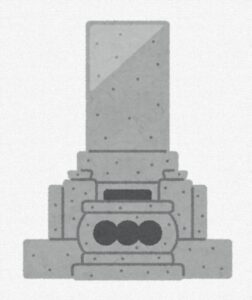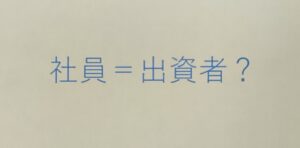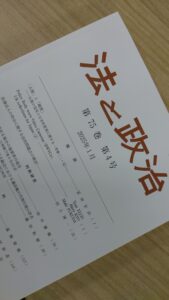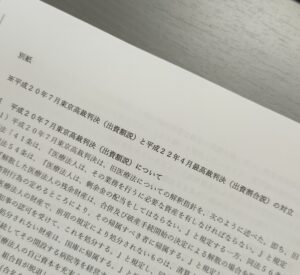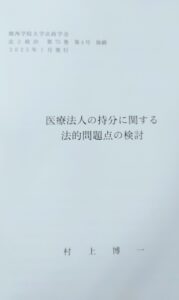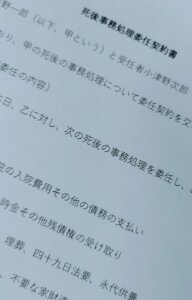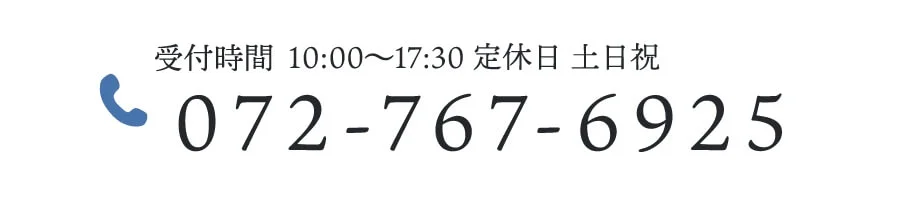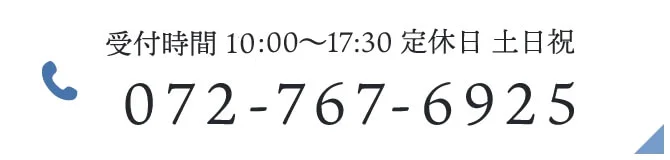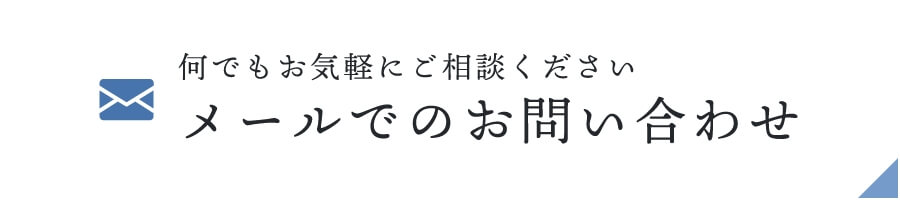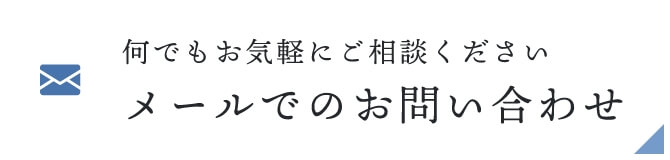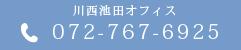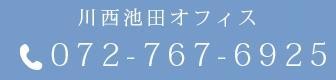遺言執行者を指定する際の法的ポイントと役割

DSC_9363
遺言書を作成することは、自身の財産や想いを未来に託すための重要な行為です。しかし、遺言書が残されていても、その内容がスムーズに実行されなければ、遺族間のトラブルや手続きの遅延につながる可能性があります。
そこで重要になるのが、**「遺言執行者」**の存在です。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う、いわば「遺言の代理人」です。
しかし、「誰でもなれるの?」「どのような役割があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。このブログでは、遺言執行者を指定する際の法的ポイントと、その重要な役割について詳しく解説します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を忠実に実現するために、必要な手続きを単独で行う権限を持つ者です。
遺言執行者がいなくても、相続人全員の合意があれば遺言書の内容を実行することは可能です。しかし、相続人が複数いる場合、意見が対立したり、手続きに協力しない人がいたりして、遺言の実現が困難になるケースが少なくありません。
遺言執行者が指定されていれば、相続人全員の同意を得る必要はなく、遺言執行者単独で手続きを進めることができます。これにより、遺産分割を巡るトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きが可能になります。
なお、遺言ですることが可能な事項については、弊所ブログ・遺言事項https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1917をご覧ください。
遺言執行者を指定する際の法的ポイント
- 遺言執行者になれる人
遺言執行者には、特定の資格は必要ありません。未成年者と破産者を除き、誰でも指定することができます(民1009条)。
- 相続人:相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能です。
- 友人、知人:信頼できる友人や知人を指定することもできます。
- 専門家:弁護士や司法書士、行政書士、税理士といった法律や税金の専門家を指定することが多いです。
専門家を指定するメリットは、法律に基づいた正確な手続きが期待できること、遺言執行に伴う煩雑な手続きを一任できることです。特に、遺産の中に不動産や非上場株式などがある場合や、相続人が複数いてトラブルが予想される場合は、専門家を指定するのが得策です。
- 指定方法
遺言執行者の指定は、遺言書に明確に記載する必要があります。
- 自筆証書遺言や公正証書遺言など、どの形式の遺言書でも指定できます。
- 遺言書には、**「遺言執行者として、〇〇(氏名)を指定する」**と明記し、本人を特定できる情報(生年月日、住所など)も記載しておくと、より確実です。
また、遺言執行者の予備として、複数の候補者を指定しておくこともできます。これにより、指定された遺言執行者が先に亡くなっていたり、辞任したりした場合でも、スムーズに手続きを進めることができます。
遺言執行者の重要な役割
遺言執行者が指定された場合、その役割は多岐にわたります。
- 遺言内容の実現
遺言執行者の最大の役割は、遺言書に記載された内容を確実に実行することです。
- 遺産目録の作成:相続財産を調査し、遺産目録を作成します(民1011条)。
- 相続人への通知:遺言書の内容を相続人全員に通知します(民1007条2項)。
- 預貯金の解約:被相続人名義の預貯金を解約し、遺言の指示に従って分配します。
- 不動産の名義変更:不動産の所有権移転登記(名義変更)手続きを行います。
➡ 但し、遺言執行者が、不動産について、名義変更を超え、現実の明け渡し(占有移転)までできるかは、難しい問題があります(この点については、弊所ブログ・相続財産の占有・管理をご覧ください、https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2125 )。
- 株式や有価証券の名義変更:被相続人名義の株式などを名義変更します。
これらの手続きは、相続人全員の同意がなくても、遺言執行者単独の権限で行うことができます。
- 相続人とのやり取り
遺言執行者は、相続人全員の代表として、相続手続きに関するやり取りを行います。
- 手続きの進捗報告:遺産調査や名義変更の進捗状況を、問い合わせがあれば、相続人に報告する義務があります(民1012条・受任者義務規定の準用→民645条)。
- トラブルの防止:相続人間の意見の対立を調整し、トラブルを未然に防ぎます。
遺言執行者がいることで、相続人同士が直接やり取りする機会が減り、感情的な対立を避けることができます。
- 遺言執行者の報酬
遺言執行者は、その職務に対する報酬を請求する権利があります。
- 遺言書に報酬額が明記されている場合は、その金額が適用されます。
- 遺言書に報酬の定めがない場合、家庭裁判所が相続財産の額や遺言執行者の職務内容を考慮して決定します。
専門家を遺言執行者に指定する場合、事前に報酬額を確認し、遺言書に明記しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ:遺言執行者は「安心」を買う手段
遺言書を作成する際、遺言執行者の指定は必須ではありません。しかし、遺言執行者を指定することは、**「残された家族にスムーズな手続きと安心を届ける」**ための重要な手段です。
特に、
- 相続人が複数いる場合
- 相続財産が多岐にわたる場合
- 相続人同士の仲が良くない場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合
には、遺言執行者を指定することをおすすめします。
遺言執行者は、単なる手続き代行者ではありません。あなたの**「最後の意思」**を、あなたの想い通りに実現してくれる、最も信頼できるパートナーです。遺言書を作成する際は、ぜひ遺言執行者の指定も併せて検討してみてください。
相続の相談は、弁護士法人村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm