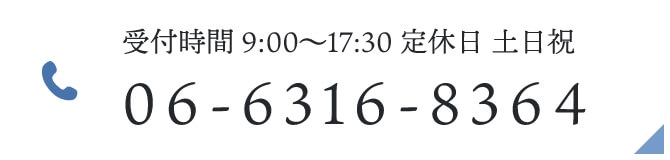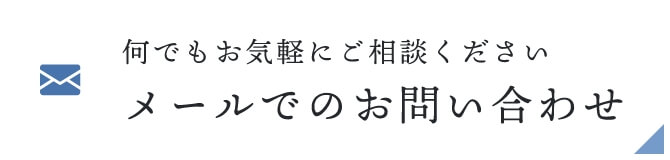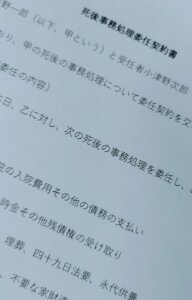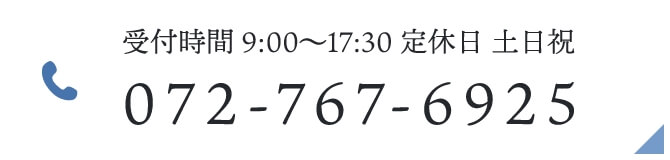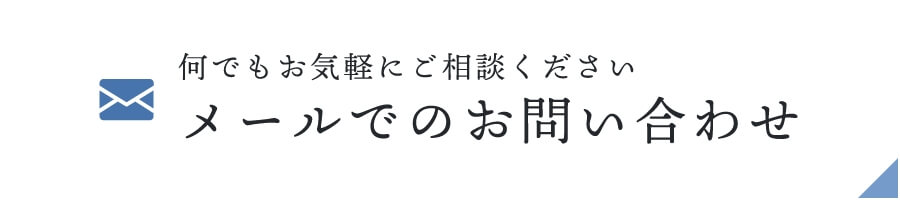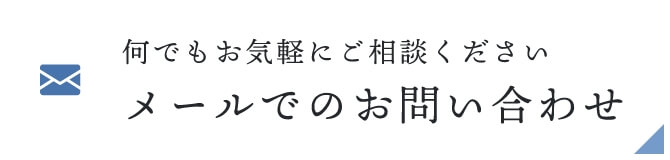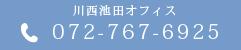遺産分割審判②対象になるか否か
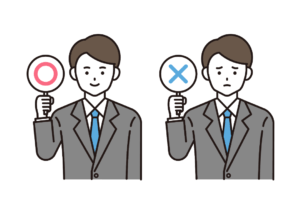
遺産分割(審判)は「遺産=相続財産」を分割する手続ですが、分割手続を経るまでもなく法定相続分に応じて当然に分割されてしまう(当然に相続人が取得する)「遺産」もあります。そこで、遺産分割(審判)の対象になるか否かという視点から、遺産類型毎に簡潔に説明します。
| 不動産・動産の所有権 | 審判の対象になる |
不動産の所有権が遺産である場合、共同相続人の「共有」になります(898条)。動産の所有権についても同様です。
ここでの「共有」が、民法249条以下に規定する「共有」と同じものかどうか、争いがありますが、最高裁が以下に述べるとおり、実務的には同じものと理解されています。ですから、共有物の利用(使用や管理等)については、民法で定められており(249条以下)、これと同様の扱いになります。
| 最3小判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁以下、家月7巻6号42頁以下 |
| 民法249条以下に規定する『共有』とその性質を異にするものではない…それ故に、遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する民法256条以下の規定が第一次的に適用せられ、遺産の分割は現物分割を原則とし、分割によって著しくその価格を損する虞があるときは…価格分割を行うことになる |
ただ、遺産分割については(249条以下の「共有」とは異なった)特別の手続が定められていいます(907条以下)。すなわち、共同相続人間で協議が調わないとき等は、その分割を家庭裁判所に請求できます(907条2項)。この請求がなされた場合、裁判所は審判という形で不動産・動産を分割します。
しかし、遺産の分割方法については、特別の手続が定められていないので、上記最高裁が述べるとおり、民法256条以下が適用され、現物分割を原則とするものの、現物をもって分割することができない場合又は分割により著しくとの価格を損する可能性がある場合は、価格による賠償により分割を行うことができます。
| 賃借権 | 審判の対象になる |
賃借権とは「賃借権(利用権)とその対価たる賃料債務、その他賃貸借契約の存続に伴って生ずるすべての契約上の債権債務を一括」した「賃借関係全体」を意味します。つまり、これは「契約上の地位」であって、単純な債権債務とは異なります。このような契約上の地位は、898条、264条にいう「(準)共有」として遺産分割審判の対象になります。
| 金銭債権 その他の可分債権 | 審判の対象にならない |
以下の判例のとおり「当然分割」されるので、遺産分割の必要もなく、遺産分割審判の対象にもならないとされています。
なお、預貯金については、次回説明します。
| 最1小判昭和29年4月8日(民集8巻4号819頁以下) |
| 不法行為に基づく損害賠償請求権について、分割債権・債務の原則を規定する427条を前提として「金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」 |
| 株式や社債 | 審判の対象になる |
株式や社債は、会社に対する一定の法的地位と考えられており、前者には「共有」に 関する定め(会社法106条)があり、後者には「相続」に関する定め(会社法691条2項)があることからして、それは遺産分割審判の対象になると解されます。
| 現 金 | 審判の対象になる |
以下の通り、最高裁の判断は「現金」そのものにも「共有」が認められるとするもので、これ自体は妥当と思われます。なので「現金」は共同相続人間で「共有」するものとして、遺産分割審判の対象になります。
ただ、問題は、それが「A遺産管理人Y」名義で預金された場合にも「共有」のままなのかという点です。この問題については、被相続人A死亡の時点で現金であったものを相続人の1人であるYが後に「A遺産管理人Y」名義でしていた預金について争われていました。
この点に関する東京高裁は「現金は、被相続人の死亡により他の動産、不動産とともに相続人等の共有財産となり…債権のように相続人等において相続分に応じて分割された額を当然に承継するものではない」としました。
そして、最高裁は以下のように判断しました。
| 最2小判平成4年4月10日家月44巻8号16頁以下、判タ786号139頁以下 |
| 相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない…原審の判断は正当 |
上記平成4年判例の理解は分かれますが「相続人が管理中の現金を不可分物と同一視しただけ」と解する見解(山田「遺産分割前に相続分相当の金銭支払を求めることの可否」民商107号6号102頁以下)が有力です。
だとすれば、本件では、預金が「A遺産管理人Y」という名義で「遺産たる金銭の管理がなされているだけで、銀行への預入によって当該相続財産の性質が変容したととらえるべきではない」という形で説明されると思います。
つまり、最高裁が指摘する「相続財産として保管」されているという点がポイントで「当該金銭がそのまま保存されることが予定され、価値として流通に置かれることが予定されていない場合」であることが重要だということでしょう(道垣内「遺産たる金銭と遺産分割前の相続人の権利」家族法判例百選[第7版]136頁以下)。
その意味で、現金の保管形態が「A遺産管理人Y」のようなもの以外であった場合には、遺産分割審判の対象にならないと解される余地があります。例えば、Yが(A遺産管理人という名を付さず)Y個人名義の口座に自らの金銭と一緒に当該現金を保管し、特に当該現金額を下回ることはないもののY個人名義の口座額に変動があったような場合には、流動性が強まっている以上Y個人に対する債権としか評価できない(従って、当然に分割されYに法定相続分を請求できる)と解される場合があるのかもしれません。
相続の法律相談は弁護士法人村上・新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm