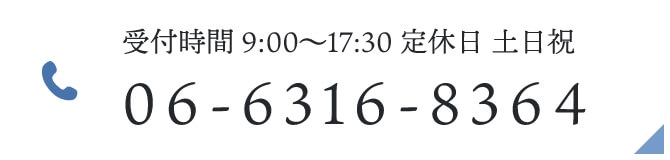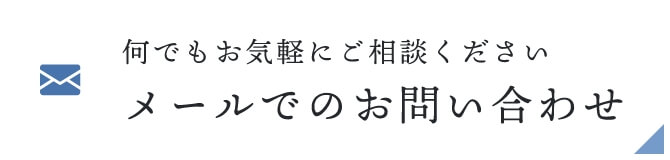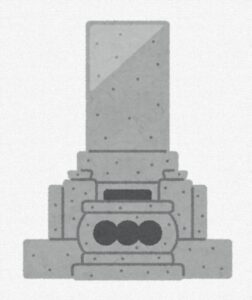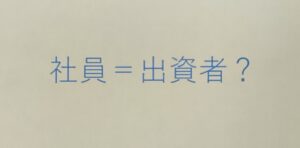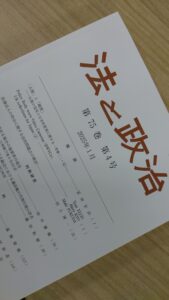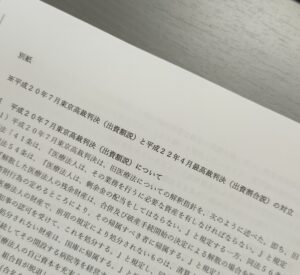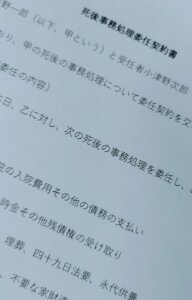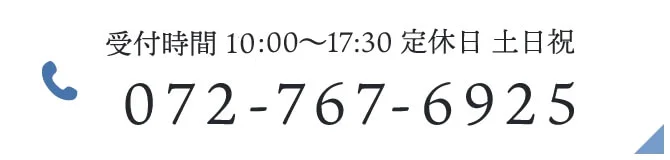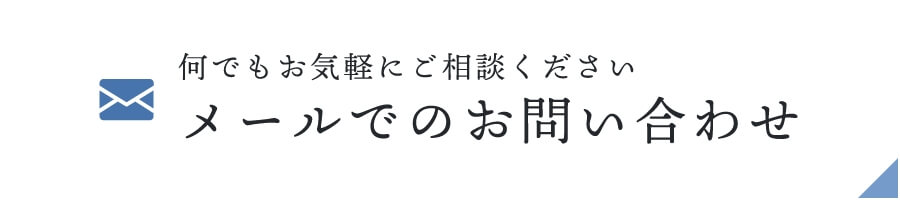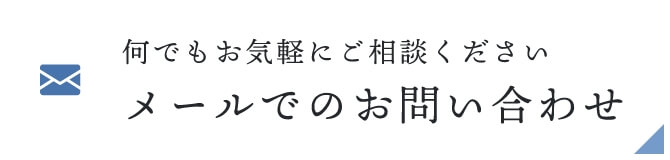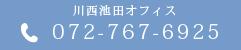自筆証書遺言③日付

遺言は厳格な要式行為として「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」とされており(960条)、その方式=要件を充たさないと無効となります。
自筆証書遺言の要件は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(968条1項)。自筆証書遺言は簡便なため、多く利用されていますが、要式性を欠いて無効になるケースも多く見られます。
そこで、自筆証書遺言の要件のうち、今回は、日付に関する問題点について検討してみたいと思います。
日付の特定ができること
日付は、遺言能力を判断する時的基準になり、また、内容の異なる数通の遺言書が存在する場合後に作成された遺言書の方が効力を有する(1023条1項)こととの関係上、その判断資料として、重要なものであるため、要件とされています。
その趣旨からすれば、日付を特定することができれば良く、「私の還暦の日」といった記載は有効となります(浦川「日付の記載」判タ688号300頁)。また「平成元年11月末」という記載も「平成元年11月30日」を表示したものとして有効となります(東地判平成6年6月28日金商979号31頁)。
しかし「吉日」という記載は無効となります(最1小判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁)。
全文自書日と日付を記載した日が異なる場合
遺言書を作成して、日付のみを後日記載したように、全文自書日と日付を記載した日にズレがある場合どうでしょうか。全文自書・署名押印をした日から8日後に日付の記載をした遺言書について、判例は「特段の事情のない限り、右日付が記載された日に成立した遺言として適式なものと解する」としています(最3小判昭和52年4月19日家月29巻10号132頁)。
日付に誤記がある場合
日付に誤記があった場合(昭和48年秋に死亡した者が同年夏の入院中に作成した自筆証書遺言について日付の年を昭和28年と記載)は「その誤記であること及び真実の作成日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない」とされます(最2小判昭和52年11月21日家月30巻4号91頁)。ただし、故意に日付を遡らせたような場合は無効とされています(前掲浦川301頁)。
最高裁の遺言解釈
遺言の要式性を強調すると単なる誤記であっても遺言が無効ということになってしまいます。ただ、最高裁は、形式的に判断するのみではなく、遺言者の真意を探求して趣旨を確定すべきであると判断しているようです。
【最高裁の判断】
最判昭和58年3月18日(家月36巻3号143頁)
「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該遺言条項の趣旨を確定すべきものである」としています。
また、判例の傾向としては、以下が指摘されています(久貴編「遺言と遺留分第1巻遺言[第2版]浦野執筆-遺言の解釈」日本評論社315頁)。
① 遺言解釈において広く外部的証拠の援用が許されるということ
② そのような外部的証拠を用いて探究される遺言者の真意については遺言の記載に一応のてがかりが求められていること
このような観点から、上記、日付に誤記があった場合の昭和52年判例を検討すれば、原審がそのまま援用した第1審の認定において、当該遺言の遺言執行者として弁護士Aと記載されていた人物が元判事であり、その退官日が昭和30年6月18日であることから、当該遺言が昭和28年に作成されたことはありえず、故に明らかな誤記である旨を指摘していることが重要視されることになります。
相続の法律相談は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm