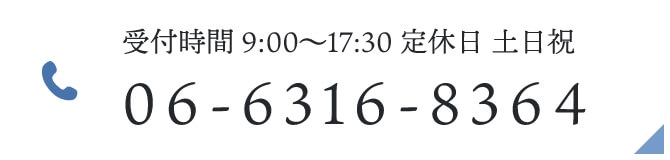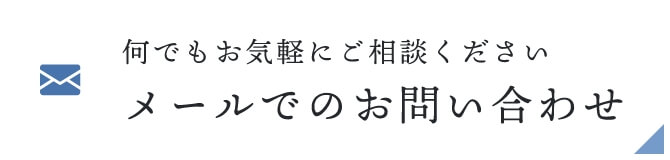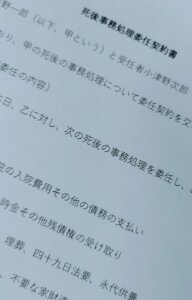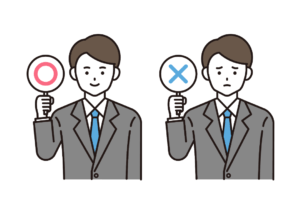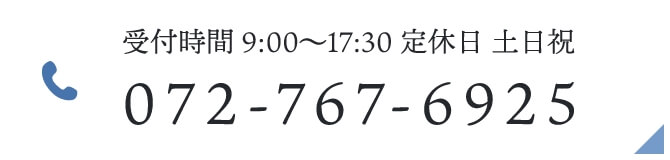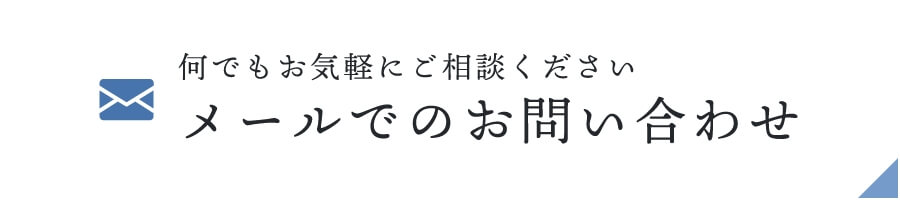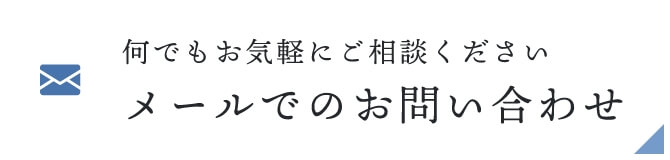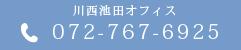遺言執行⑤特定財産承継遺言
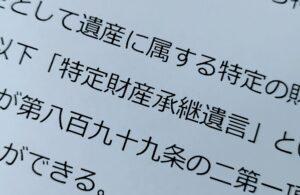
1 特定財産承継遺言に関する条文は、以下のとおりです(下線は、平成30年に改正された点です。)。
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 ポイント
(1)特定財産承継遺言とは
遺言等を作成する公証人役場の実務の中で、例えば、甲という特定不動産を「相続させる」という遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)の形が編み出され、その法的性質について、最高裁は、以下の様なものだと判断しました。
| 最2小判平成3年4月19日民集45巻4号は、甲不動産のように「特定の遺産」についてなされた「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法を定めた遺言(908条)ではあるが「他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから…特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該相続人に相続により承継されるものと解するべきである」としました(裁判長の名前を採って、香川判決とされています。)。 |
そこで、平成30年改正法は、このような理解を前提に「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」を「特定財産承継遺言」とすることにしました(1014条2項)。
(2)遺言執行の余地はあるのか?
すると、次のような疑問が湧きます。即ち、特定財産承継遺言について、相続させるとされた相続人(以下、受益相続人といいます。)は、遺贈の場合と異なって、直ちに遺産が相続により承継されるため、他の相続人の協力を必要とせず、この遺言書を利用して単独で相続を原因とする所有権移転登記が可能です(不動産登記法62条)。
そうなると、特定財産承継遺言については、遺言執行者の出る幕がないのではないかという疑問です。
この疑問に答えたのが、相続させる旨の遺言について下された最1小判平成11年12月16日民集53巻9号1989頁です(以下、平成11年判決)。
| 平成11年判決・事案の概要(遺言執行者の職務に関する事実に限って簡略化) |
| 被相続人が不動産を有しており、その子としてA、Bがいました。当該不動産について、Aに「相続させる」旨の遺言(以下、新遺言といいます。)があったのですが、Bに「相続させる」旨の旧遺言があったので、これをBが利用して登記を自己名義にしました。 |
新遺言には遺言執行者がいて、その者が乙名義の登記抹消を求めることができるかどうかが争われました。
| 平成11年判決 |
| 登記実務上、相続させる遺言については不動産登記法二七条により甲が単独で登記申請をすることができるとされているから、当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者の職務は顕在化せず、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しない…。しかし、本件のように、Aへの所有権移転登記がされる前に、他の相続人(B)が当該不動産につき自己名義の所有権移転登記を経由したため、遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には、遺言執行者は、遺言執行の一環として、右の妨害を排除するため、右所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができ、さらには、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできると解するのが相当である。この場合には、Aにおいて自ら当該不動産の所有権に基づき同様の登記手続請求をすることができるが、このことは遺言執行者の右職務権限に影響を及ぼすものではない |
つまり、「相続させる」旨の遺言がされた場合、受益相続人は単独で登記名義の移転を申請できるため、原則として、遺言執行者に登記手続を行う必要がありません。平成11年判決は、傍論で「当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者の職務は顕在化せず」と述べましたが、それはこのような意味です。ただ、例外として、下線部のような事態が生じた場合には、遺言執行者による登記手続の必要性が認められるというものです。
(2)改正法の考え方
ところが、改正法は、先ず889条の2‐1項にて「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない。」としました。
従前、特定財産承継遺言は、香川判決により「何らの行為を要せずして…相続により承継される」ことから、特定の不動産を取得した受益相続人は「登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる」とされていました(最2小判平成14年6月10日家月55巻1号77頁)が、この前提が改められました。
結局、特定財産承継遺言がされた場合でも、登記名義の変更をする必要性が高まったということになり、だとすれば遺贈の場合と異ならないことから、1014条2項において、特定財産承継遺言についても、遺言執行者は、対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされました(ただ、従前と同じく、受益相続人が単独で登記名義を移転することも可能です。)。
(3)預貯金の取扱い
このようにして、特定財産承継遺言についても、遺言執行者に対抗要件具備行為が認められた訳ですが、例えば、その財産が預貯金だとすると、それは預貯金名義の書換えということになるのでしょうが、金融機関の中には預貯金名義の書換えに消極的なところも存在します。ただ、それでは遺言の内容を実現するのが難しくなることもあるので、遺言執行者に預貯金の「払戻し・解約」の権限も認めました(1014条3項本文)。
ちなみに、この1014条3項は「預貯金債権の遺贈がされた場合には適用されない。」というのが立法担当者の見解です。例えば、亡Aの預貯金がBに遺贈がされたときに遺言執行者が存在しない場合であれば、預貯金の遺贈義務を履行するのはAの相続人Cになるところ、受遺者であるBと利害が対立する相続人Ⅽに預貯金の払戻し解約権限を認めるのは、必ずしも相当でないとされるからです(堂園外編著「一問一答新しい相続法〔第2版〕」商事法務119頁)。
(4)施行日
本条(1014条)の施行日は、令和元年7月1日ですが、2項から4項までの規定は「施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。」とされています(附則8条2項)。
相続の法律相談は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm