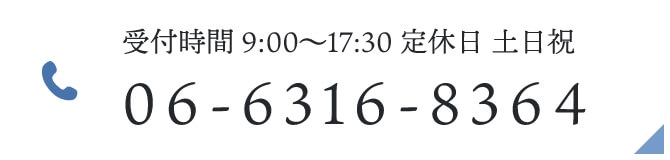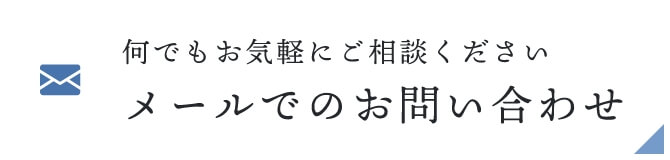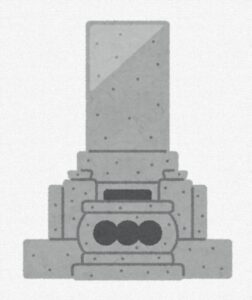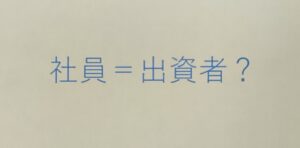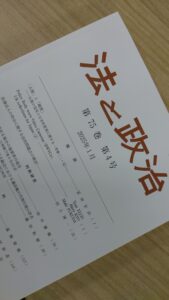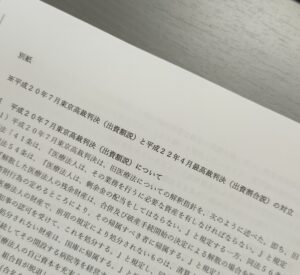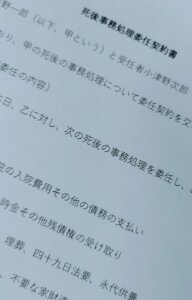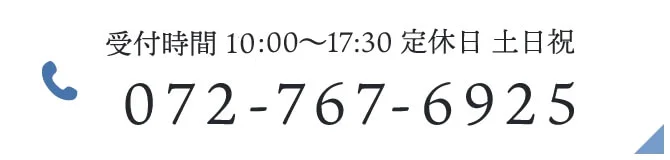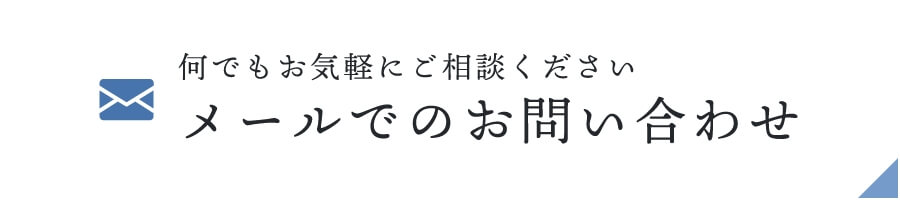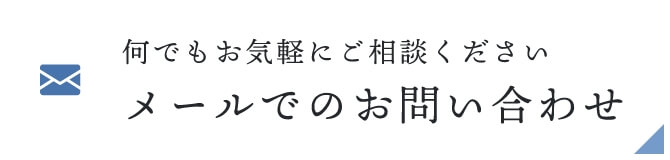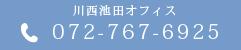相続欠格②遺言書を偽造・変造した場合の判例

昭和56年判決の事案と内容
では、遺言書を「偽造、変造」した場合はどうでしょうか。この点に関する昭和56年最高裁判決(最2小判昭和56年4月3日民集35巻3号431頁)の事案は、以下のとおりです。
| A(被相続人)には、妻X1と3人の子X2、Y、Bがいたというもので、X1、X2(以下、Xらといいます。)及びYとBの間には別件訴訟が係属していました(Xら及びYは、同じ弁護士Cを訴訟代理人としていました。)。 ところが、A死亡後にAの自筆証書遺言が発見され、その遺言内容はBとの訴訟でXら及びYにとって有利なものでしたが、Aの押印がありませんでした。そこで、Cのすすめにより、Xらは、遺言検認申立をしたのですが、形式不備(A名下の押印、二個の訂正箇所の押印、一葉目裏と二葉目表の契印等)も指摘されていたことから、検認日までにAの押印をX1がしてしまったというものです。 ただ、その遺言内容は、Yとの関係ではXらに不利であったため、後日、Xらは、Yとの関係でその無効確認請求訴訟を提起した。 |
この訴訟の控訴審において、X1が遺言書を「偽造又は変造」した相続欠格者として遺言無効訴訟を提起する資格がないのではないかが争われたところ、控訴審は偽造、変造の事実を否定しました。
そこで、Yが上告したところ、昭和56年判決は、以下の通り「偽造、変造」の事実を認めたものの、結果として原判決を支持し、遺言無効確認の訴えを認容しました。
|
二重の故意の理論を採用していないこと
昭和56年判決は、相続欠格にあたるかどうかを「遺言者の意思を実現させるか」という視点から判断したようにもみえます。問題は、後に平成9年判決が「二重の故意の理論」を採用したことから、今後は、遺言書の「偽造、変造」においても「二重の故意の理論」が適用されるかというと「そうではない」と考えられています。昭和56年判決は、現在も生きています。そこで、昭和56年判決をどのように
理解するか重要になります。
昭和56年判決の理解
前述したとおり、昭和56年判決は「遺言者の意思を実現させるか」という点を重視しているかに読めます。しかし、そのような解釈を貫くと、昭和56年判決事案のように遺言の「形式不備」を補うための行為は、すべて許されることにもなりかねませんが、それは不当です。令和元年に施行された現行相続法によれば、若干緩和されているものの(自筆証書遺言におけるワープロ等による財産目録の許容-968条2項本文)、遺言には一定の方式が求められています(自筆証書遺言は、全文、日付、氏名の自書と押印、968条1項)。従って、たとえ遺言者の意思が明確であったとしても、方式を欠けば遺言書として無効でなのは明らかで、それを補うことは原則として許されないからです。
では、昭和56年判決が、Ⅹ1の行為(追加押印)を相続欠格事由にあたらないと考えたのは何故か、平成9年判決が述べるように5号の趣旨は遺言に関し「著しく不当な干渉行為」をしたことに対する民事制裁ですから、ただ、Ⅹ1のした押印(遺言書の形式不備を補う)が、Ⅹらだけでなく「Yにとっても有利なもの」だったからだと思われます。そのような考え方を取れば「二重の故意」の理論を前提としなくても、平成9年判決とは矛盾しない形で説明できるかと思います。
なお、他の相続欠格に関する投稿はこちら
相続欠格①遺言書の破棄・隠匿 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/910
相続欠格③wの悲劇 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1334
宝塚市・川西市の相続相談は、村上新村法律事務所・川西池田オフィスまで
https://g.page/murakamishin?gm
大阪市・福知山市の相談はこちら
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/