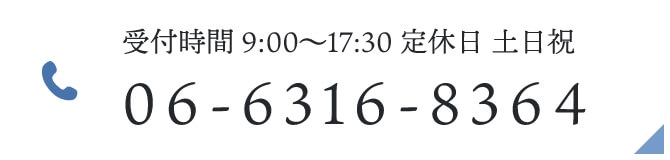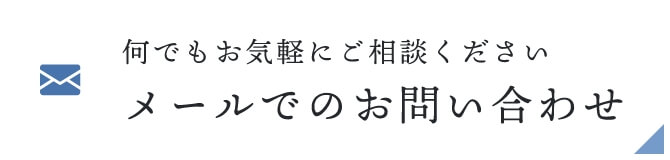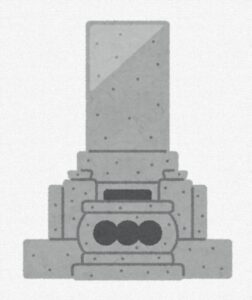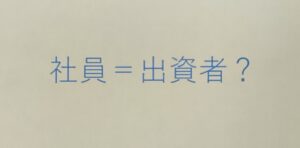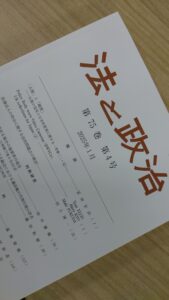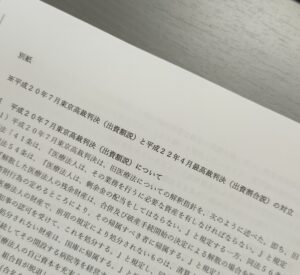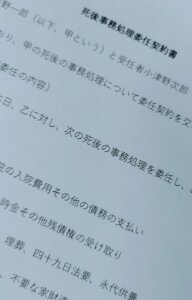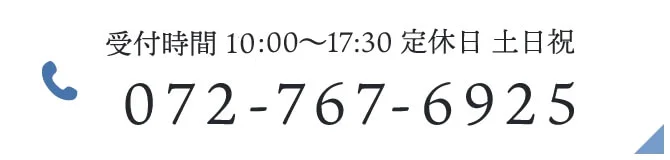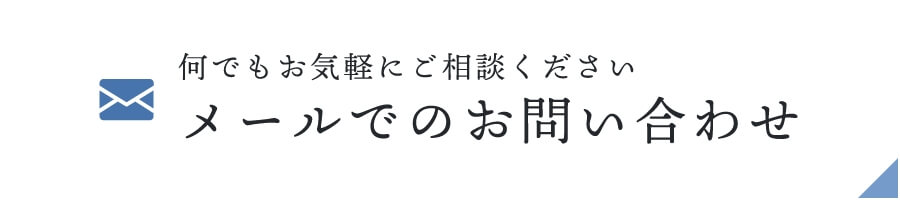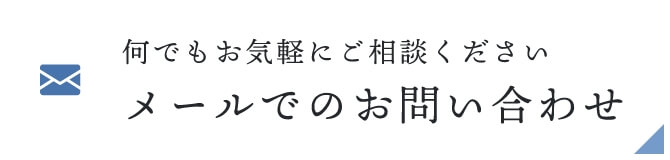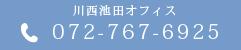遺留分⑥事業承継に関する民法特例
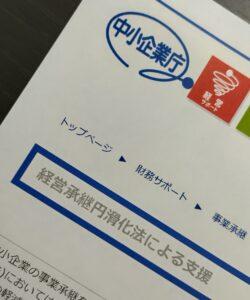
DSC_1744
経営承継円滑化法(以下、単に法といいます。)は「中小企業について…遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより…経営の承継の円滑化」を図るものとして、平成20年に施行されました。そこで1つの柱である「遺留分に関する民法の特例」について、簡潔に説明したいと思います。
事業承継における相続制度の問題
1)遺言がない場合
遺言の動機・目的の1つとして、資産を細分化させないことがあります。
例えば、Aが100パーセント株式を有する会社Zの代表者でマンション甲を所有し賃貸経営していたとします。Aの子としてB、Cが存在した場合、Aが死亡すれば、均分相続の建前により、B、Cがそれぞれ2分の1ずつ法定相続(887条1項、900条1号)する形になり、遺産分割が終了するまではZの株式はB、Cが準共有(264条)ということになります。しかし、会社法106条によれば、権利を行使する者一人を定めなければ、当該株式についての権利を行使することができません。このため、B、Cの意見対立があると、結局、Zの代表者を誰にするかも含め経営が立ち行かなくなり、最悪の場合はZ株式等を換価し金銭で分割しなければならないという事態も生じます。
そうなると、せっかく築いたZの経営も失われていくことになります。
2)遺留分制度の問題点
この場合において、例えば、Aが「Z株式の全てをBに相続させる」旨の遺言をしておけば、資産を細分化させることなく、Z株式はB一人に帰属するので、そのような事態は生じないということです。ただ、この遺言スキームには、遺留分制度による問題があります。
相続法改正前であれば、Cが遺留分が存在するとして「遺留分減殺請求権」を行使した場合、Z株式につきCが直接権利(Aにその他の財産がないとすればZ株式の4分の1)を取得する可能性がありました。結局、遺言をしたとしても遺言をしなかった場合と似たような事態が生じ得ました。Aが死亡した後では、B、Cの関係調整はより難しくなるだろうという問題もありました。
現在の相続法では、Cは「遺留分侵害額請求権(金銭支払請求権)」を行使できるに過ぎません(1046条1項)。従って、従前より問題は減りましたが、4分の1とはいえZ株式の価額が高ければ、Aとしても高額の資金調達が必要になり、それはZ会社の経営に影響することも考えられます(遺留分侵害額請求権については、こちらをご参照ください。https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1259/ )。
3)特別受益の問題
それに加えて、特別受益の問題もあります。
即ち、遺留分算定の基礎となる財産額には、生前贈与された財産も合算します。そして、配偶者や子といった法定相続人への贈与は相続の前渡し分(特別受益)とされ合算しなければなりません(遺留分と特別受益の関係については、こちらをご参照ください。https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1224/ )
相続法改正前であれば、BがAの相続人である限り、何年前の贈与であっても合算の対象となっていました。現在の相続法1044条によれば、それは「10年間」における贈与に限定されていますが、10年間はそれなりの期間ですし、同条ただし書は「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは」10年前の日「より前にしたものについても、同様とする」としていて、10年以上前の贈与も合算の対象にしなければならない可能性があります。
ちなみに、この場合、合算される財産の評価時点は贈与時ではなく相続開始時となります。すると、後継者(例えば子)に生前贈与された株式の価値が、後継者自身の貢献により上昇した場合であっても、価値が上昇した分を含めて遺留分侵害額請求権の金額を算定することになります。
これでは、生前贈与を受けた後継者は、その努力により株式の価値を高めても、後継者以外の者の遺留分侵害額請求権の金額が増えるという皮肉な結果になってしまいます。
遺留分に関する民法特例
そこで、相続紛争や自社株式の分散を防止し、後継者にスムーズに事業承継させるべく法4条以下で遺留分に関する民法の特例が定められました。この特例は、Aから後継者Bへの生前贈与によるスキームです。
この特例を受けるためには、「特例中小企業者」の「旧代表者」が「後継者」にその株式または持分(以下、株式等)を贈与した場合、推定相続人の全員が一定の合意をし、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
1)対象者
特例中小企業者
中小企業(※)で、非上場、かつ、3年以上事業継続している必要があり、これを、特例中小企業者といいます(法3条1項、法施行規則2条)。
※資本金等、従業員数、業種によって定まるもので、中小基本法2条1項に定めるものとほぼ同じです(法2条、中小企業の具体的要件は、こちらをご覧ください。
https://m2-law.com/blog/1408/ )。
旧代表者
特例中小企業の代表者であった者(但し、これから事業承継をさせようとしている者も含める必要があるので、現代表者でも可とされています。)であり、その推定相続人(※)のうち、少なくとも一人に対し、特例中小企業者の株式等を贈与したことがある者をいいます。
※推定遺留分権利者であり、旧代表者の兄弟姉妹等を除きます。かかるスキームは、遺留分対策のものであるため、子等がおらず兄弟姉妹等に事業承継をさせる場合であれば、前述した遺言のみによる対応で足りるからです。
後継者
後継者とは、旧代表者の推定相続人であって、旧代表者から株式等の贈与等を受け、当該特例中小企業者について、総株主等の議決権の過半数を有している、代表者である者をいいます。
2)適用要件
① 現実の贈与等
対象株式等(合名会社、合資会社、合同会社といった持分会社の持分も含むことから株式等という表現をとっています。)は、旧代表者(A)から後継者(B)に現実に贈与等が履行されたものでなければなりません(事業承継研究会「事業承継問題の研究」大阪弁護士会14頁)。なお、贈与等という表現は、例えば、旧代表者が祖父として孫が後継者となる場合その祖父が亡父に贈与しその孫が相続等したものも含むという意味で用いられています。
② 民法特例に係る合意
後継者が、旧代表者から贈与等を受けた株式等によって当該特例中小企業者の総株主等の議決権の50%を超える数を有するに至った場合、当該株式等について、旧代表者の他の推定相続人との間で、書面によって、以下の合意をすることができます(法4条1項)。
| 除外合意(同項1号) | 当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと |
| 固定合意(同項2号) | 当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額とすること |
なお、固定合意をする際は、弁護士、公認会計士等が「合意の時の相当な価額として証明」することが必要です。
相続の法律相談は、村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/
事業再生・法人破産・債務整理サイト