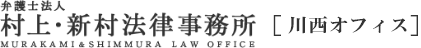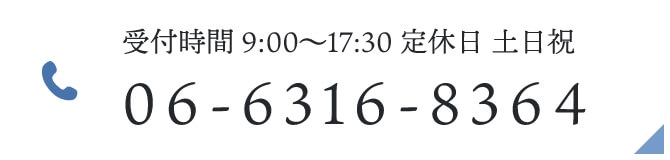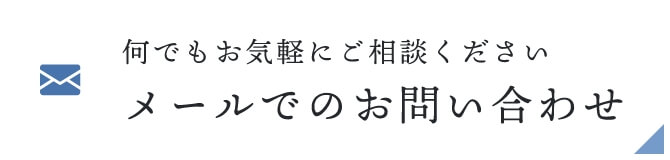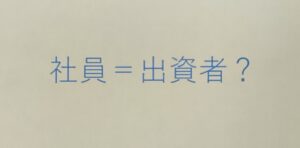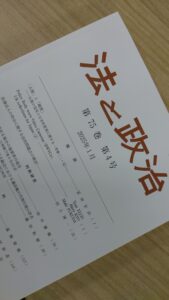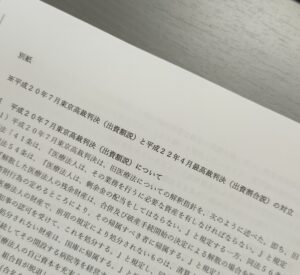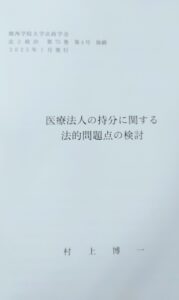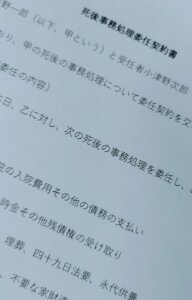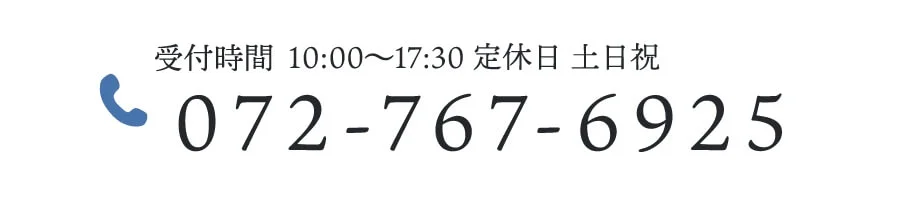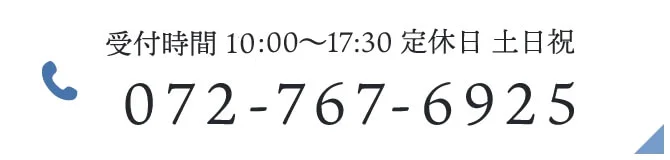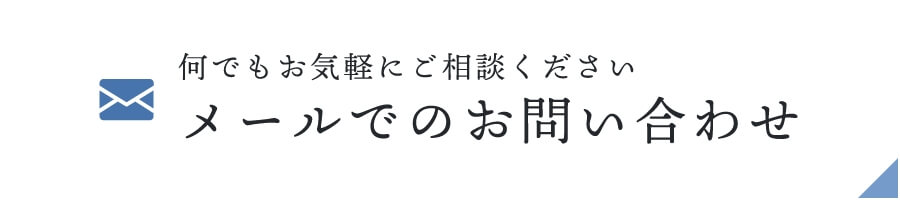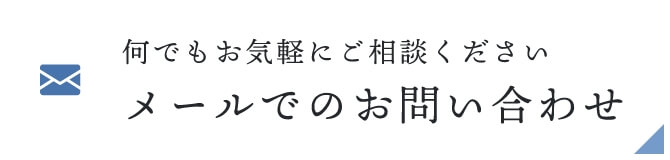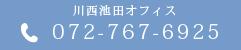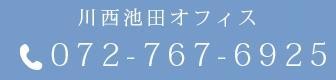祭祀財産の承継
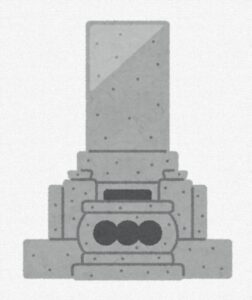
はじめに
遺産相続と聞くと、多くの人が「預貯金や不動産、株式などのプラスの財産をどう分けるか」を思い浮かべるでしょう。しかし、相続財産の中には、故人が大切にしてきた**「祭祀財産」**と呼ばれる、少し特殊な財産も含まれます。祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇、位牌、家系図など、先祖を祀るために必要な財産のことです。これらは、金銭的な価値だけで測れない、故人の想いと家族の歴史が詰まった大切なものです。
※ 遺体・遺骨を祭祀財産と同様に考えていいのかについては、争いがあります。
この祭祀財産は、通常の相続財産とは異なり、**遺産分割の対象にはなりません。**そのため、「誰が引き継ぐべきか」という問題が、相続人全員の話し合いでは解決しにくいケースも少なくありません。本コラムでは、祭祀財産の承継者を法的に決定する方法と、その際に知っておくべきポイントについて解説します。
祭祀財産と一般の遺産の違い
民法897条では、祭祀財産について、以下のように定められています。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従い又は家庭裁判所の定めたところに従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。
この条文が示すように、祭祀財産は「相続財産(民法896条)とは別個の財産」であり、法定相続分や遺留分の対象にはなりません。相続放棄の規定の適用もありません。そのため、特定の「祭祀承継者」が単独で引き継ぐことになります。
祭祀財産が通常の遺産分割協議の対象とならないのは、祭祀を絶やすことなく、円滑に承継させることを目的としているからです。
祭祀承継者を決定する3つの方法
祭祀承継者を決定する方法は、民法897条に基づき、以下の3つの順序で判断されます。
- 故人(被相続人)の指定
最も優先されるのは、故人が生前に祭祀承継者を指定していた場合です。
- 遺言書による指定:遺言書に「祭祀承継者を長男である○○と指定する」のように明確に記載されている場合、その内容が最も優先されます。
- 書面・口頭による指定:故人が生前に、明示・黙示で指定していた場合も有効とされます(但し、口頭の場合や黙示の場合、客観的に明確とはいえないので、そのような指定があったこと自体が争われることもあるでしょう。)。
- 生前行為による指定:故人が生前に、墓地の永代使用権の名義を特定の人物に変更していた場合なども、指定があったと判断されることがあります。
故人の指定をめぐって相続人同士で争いが生じる可能性があるため、遺言書による明確な指定が最も確実な方法と言えます。
- 慣習による決定
故人の指定がない場合、慣習に従って、従って承継者を決定します。慣習とは、被相続人の住所地の慣習(長男が承継者になる地域)や業に特有の慣習(代を継いだ者が承継者になる伝統)等があります。しかし、現代社会においては、家族の形が多様化し、特定の慣習が確立していないケースも増えています。慣習による決定をめぐって争いが生じた場合、次の「家庭裁判所による決定」に進むことになります。
- 家庭裁判所による決定
故人の指定がなく、慣習も明確ではない場合、または慣習による決定に争いがある場合は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判官が承継者を決定します。
申立ての流れ
- 申立て:相続人や利害関係人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に**「祭祀承継者指定の申立て」**を行います。
- 調停:まずは調停で話し合いが行われ、相続人同士等の合意形成が試みられます。
- 審判:調停が不成立の場合、審判へと移行し、裁判官が承継者を決定します。
家庭裁判所が考慮するポイント
家庭裁判所は、承継者を決定するにあたり、以下の点を総合的に考慮して判断します。
- 故人との関係:故人との親密さ、故人が生前に誰に世話になっていたか。
- 承継者の意思:祭祀を承継する意思があるか。
- 経済力:墓地の管理費や仏壇の維持費用などを支払う経済力があるか。
- 祭祀の主宰能力:承継者が、祭祀を主宰するに足る人格や能力を備えているか。
裁判官は、これらの客観的な事実に基づいて、祭祀を円滑に主宰できる**「最もふさわしい者」**を選任します。
祭祀承継者をめぐるトラブルを避けるために
祭祀財産は、金額の多寡にかかわらず、家族の感情が大きく絡むデリケートな問題です。トラブルを未然に防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- 遺言書での指定:故人が生前に遺言書で明確に祭祀承継者を指定しておくことが、最も確実な方法です。
- 生前からの話し合い:家族や親族間で、将来の祭祀承継について話し合い、互いの意思を確認しておくことが重要です。
- 専門家への相談:祭祀承継をめぐってトラブルが起こりそうな場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ:祭祀承継は「想いを引き継ぐ」こと
祭祀財産の承継は、単なる財産の承継ではなく、故人や先祖代々の**「想い」**を未来へ引き継ぐ大切な行為です。
祭祀承継者をめぐる争いは、遺族間の感情的な対立を深め、故人を悲しませることになりかねません。
故人の意思を尊重し、円満に祭祀を承継させるためにも、生前からの準備と、もしもの際の適切な法的知識が不可欠です。
このコラムが、家族間の話し合いのきっかけとなり、故人の想いを未来へつなぐ一助となれば幸いです。
相続の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm