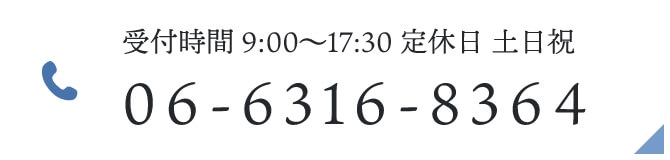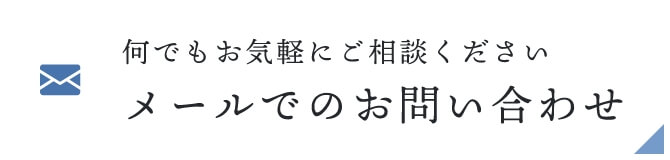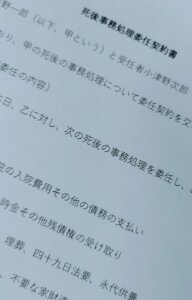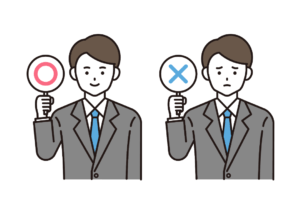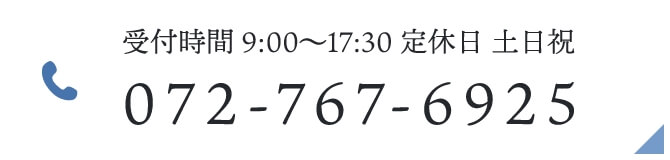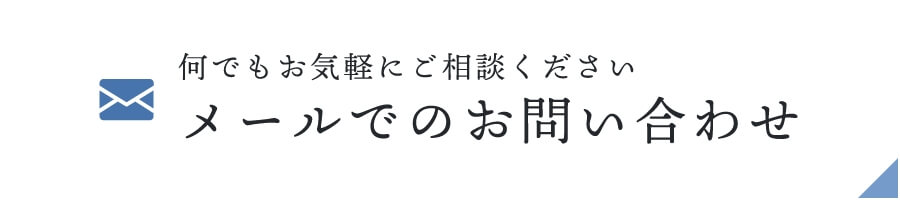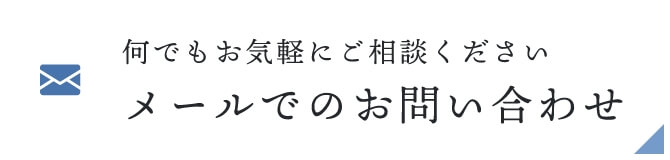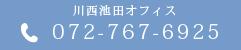男性死亡後に保存精子を用いて人工生殖により生まれた子

1 はじめに
(1)生殖補助医療は進展し、精子等を凍結し半永久的に保存することが可能になり、死後生殖も出来るようになりました。
そこで、例えば、夫A妻Bの夫婦において、夫Aが、生殖補助医療の中で、精子凍結保存後死亡。それから1年後に妻Bが、生殖補助医療を受け、保存精子により子Ⅽを懐胎、その後出産。この場合の子Ⅽに夫Aとの間で父子関係が認められるかが、問題となります。
(2)前提として、民法772条1項は「夫が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」としていますが、Aの死亡によりBとの婚姻関係は解消されます。従って、Ⅽは婚姻中に懐胎した子ではありません。また、同条2項は「婚姻の解消…の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」としていますが、Ⅽは1年後に懐胎しているので、この規定も適用されません。ただ、民法787条は「父…の死亡の日から三年を経過」するまでは「子…又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。」としています。Bは、出産しているのですから、Ⅽとの間に母子関係があり、Ⅽの法定代理人になります(818条1項、824条)。そこで、具体的には、BがⅭの法定代理人として、検察官を被告(人事訴訟法42条1項)として提起した死後認知の訴えが、認められるか問題になります。
2 平成18年最高裁判決
(1)この点、最2小判平成18年9月4日(以下、平成18年最高裁判決といいます。)は、以下のように述べました。
即ち「民法の実親子に関する法制は、血縁上の親子関係を基礎に置いて、嫡出子については出生により当然に、非嫡出子については認知を要件として、その親との間に法律上の親子関係を形成するものとし、この関係にある親子について民法に定める親子、親族等の法律関係を認めるものである。ところで、現在では、生殖補助医療技術を用いた人工生殖は、自然生殖の過程の一部を代替するものにとどまらず、およそ自然生殖では不可能な懐胎も可能とするまでになっており、死後懐胎子はこのような人工生殖により出生した子に当たるところ、上記法制は、少なくとも死後懐胎子と死亡した父との間の親子関係を想定していないことは、明らかである。すなわち、死後懐胎子については、その父は懐胎前に死亡しているため、親権に関しては、父が死後懐胎子の親権者になり得る余地はなく、扶養等に関しては、死後懐胎子が父から監護、養育、扶養を受けることはあり得ず、相続に関しては、死後懐胎子は父の相続人になり得ないものである。また、代襲相続は、代襲相続人において被代襲者が相続すべきであったその者の被相続人の遺産の相続にあずかる制度であることに照らすと、代襲原因が死亡の場合には、代襲相続人が被代襲者を相続し得る立場にある者でなければならないと解されるから、被代襲者である父を相続し得る立場にない死後懐胎子は、父との関係で代襲相続人にもなり得ないというべきである。このように、死後懐胎子と死亡した父との関係は、上記法制が定める法律上の親子関係における基本的な法律関係が生ずる余地のないものである。そうすると、その両者の間の法律上の親子関係の形成に関する問題は、本来的には、死亡した者の保存精子を用いる人工生殖に関する生命倫理、生まれてくる子の福祉、親子関係や親族関係を形成されることになる関係者の意識、更にはこれらに関する社会一般の考え方等多角的な観点からの検討を行った上、親子関係を認めるか否か、認めるとした場合の要件や効果を定める立法によって解決されるべき問題であるといわなければならず、そのような立法がない以上、死後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係の形成は認められないというべきである。」というものです。
(2)平成18年最高裁判決を整理すると、死後懐胎子Ⅽついては、父Aは親権者でなく、父から扶養等も受けられません。
また、民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としていますが、ここでの胎児は、続開始時に胎児であった場合を意味します(同時存在の原則)。従って、ⅭにはAの相続権もありません。そして、平成18年最高裁判決は、代襲相続を「被代襲者が相続すべきであったその者の被相続人の遺産の相続にあずかる制度」と理解し、代襲相続も否定しました。
以上から、死後懐胎児には、法律上の親子関係における基本的な法律関係(親権・扶養・相続)が生じる余地がないものとして、立法がない限り、法律上の親子関係は認められないと解した次第です。
(3)ちなみに、平成18年最高裁判決の事案は、平成9年に婚姻した夫婦が、その直後から不妊治療を開始していたところ、以前から白血病の治療を受けていた夫が骨髄移植をすることになり無精子症になることを危惧したことから、平成10年6月に精子を冷凍保存しました。術後、平成11年5月には不妊治療を再開する手はずを整えていたものの、平成11年9月に夫が死亡したにもかかわらず、平成12年になって妻が病院にその事実を伝えないまま体外受精をし、平成13年5月に子を出生したというものです。夫は、生前から「自分が死亡しても、再婚しないのであれば子を生んでほしい」「自分に何かあった場合には、冷凍保存精子を用いて子を授かり、家を継いでもらいたい」といっていたようでした。
従って、徒に保存精子を用いたともいえず、このような酌むべき事情があったことから、平成18年最高裁判決の原審(高松高裁)は、死後懐胎子からの認知請求は「認知を認めることを不相当とする特段の事情のない限り、子と父との間に血縁上の親子関係が存在することに加えて、当該死後懐胎子が解任するに至った人工生殖について父の同意があることが必要であり、かつ、それで足りる」として、死後認知請求を認めましたが、平成18年最高裁判決は、これを立法事項と考え、高松高裁の判断を退けたというものです。
3 平成18年最高裁判決以降の取扱い
(1)日本産科婦人科学会は、平成19年4月、凍結保存精子は、使用の場合には本人の生存および意思を確認すること、本人が死亡した場合に廃棄されること等を、見解として発表しています。
(2)平成18年最高裁判決が「死後懐胎児と死亡した父との間の法凍結保存精子は律上の親子関係の形成は認められない」としている以上、死亡による「婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子」であったとしても、死後懐胎児であれば、民法772条は適用されないことになると解されます。
相続の相談は村上新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
事業再生・債務整理サイト
交通事故サイト
https://kawanishiikeda-law-jiko.com/